アボリジニのコスモロジーと高位イニシエーション [伝統文化のコスモロジー]
オーストラリアの原住民のアボリジニは、世界でも最も古い文化を残してきた人々の一つです。
アボリジニの社会は、男性も女性も多段階のイニシエーションを備えていて、「ドリーミタイム」と呼ばれる霊的次元に深く同調するように、生涯をかけてその成長を目指します。
アボリジニの文化は人類の原型的な文化ですが、精神的な側面では完成された文化でしょう。
<トーテム先祖の創世神話>
アボリジニの文化は、トーテミズムの特徴を持っています。
「トーテム先祖」は、特定の氏族の先祖であり、特定の動物や植物、天体、自然などの先祖でもあり、両者の魂がそこに帰り、そこから生まれる存在です。
「トーテム先祖」は、神話の時代に人間の姿になったり、動物の姿になったりしましたが、その性質は、人間には内面に、動物には外面に与えられます。
ただ、アボリジニには、この氏族のトーテム以外にも、性別(母系半族、父系半族)に関わるトーテムと、「パワー・アニマル(守護霊)」としての個人のトーテムがあります。
また、アボリジニにおいては、トーテムは、人間を動物だけでなく、土地と強く結びついています。
アボリジニの神話では、「トーテム先祖」のは、多くは地下から現れて(一部は天から)、長い旅をし、地形を作り、聖地を作り、名づけを行い、法(タブー)と儀礼をもたらしました。
そして、人間と動物を生み、また、「霊的子供」を生みました。
「霊的子供」は、水場などにいて、近くを訪れた女性の中に直接入ったり、男性が狩る動物の中に入って食されることで女性の中に入ったりして、人間の赤ん坊として生まれます。
「トーテム先祖」が旅した道は、「ソングライン」とも呼ばれ、これに沿って歩いて狩りを行います。
また、この道は交易のネットワークにもなりました。
聖地を多くは、井戸や泉などの水場であり、そこは人間が生まれ、死者が一旦戻って行く場所です。
また、聖地は、動・植物を殺さないタブーの場所でもあります。
アランダ族の神話では、原初に、水溜りに胎児のような原人間達が、つながった状態で存在しました。
また、「トーテム先祖」が大地の下で眠っていました。
「ドリームタイム」が始まると、この原人間は、大地から生まれて、放浪して大地を形作りました。
そして、「トーテム先祖」がこの原人間を引き離して、口・目・鼻を開けました。
こうして人間が誕生しましたが、最初の人間達は文化を作って英雄になりました。
また、「トーテム先祖」は、その歩んだところどころに「霊的子供」を残しました。
「トーテム先祖」は地下へ帰りましたが、彼らが地上で誕生した地と帰還した地は、祭儀の場所となりました。
アボリジニが持っている「チュリンガ」という祭儀は、この「トーテム祖先」の通った道や宿の場所が表現されています。
別の「トーテム先祖」の神話では、眠っている「トーテム先祖」の体にトーテム動物達が入ったり、体からトーテム動物達が生まれたりします。
そして、人間は、「トーテム先祖」の脇の下から生まれます。
また、「トーテム先祖」が「チュリンガ」になり、その中に「霊的子供」がいます。
このように、「トーテム先祖」は、各氏族にとっての霊魂、文化、大地の環境の創造力そのものであり、その原型的存在です。
<虹蛇>
北部、中央部など各地の諸部族は、様々な名前で呼ばれる「虹蛇」を信仰しています。
「虹蛇」は、生命を与える水の化身であり、創造と豊穣、霊魂の根源的存在です。
「虹蛇」は、両性具有的存在ですが、その外的形態は男性(男根)であり、内部は女性であるとも考えられています。
また、水晶との対比した場合には女性原理とされます。
「虹蛇」は、大地と宇宙のエネルギーであり、池の底に住み、大地と天空を結びます。
「ドリームタイム」には、雨を司って、洪水をもたらしました。
クンウィンジク族の神話によれば、原初の創造的存在である「インガルナ」が「虹蛇」を生み、「虹蛇」が万物を生みました。
ある部族の神話では、「虹蛇」から生まれた口のない原人間が、大地を作り、「霊的子供」を残して、「虹蛇」に戻りました。
また、ある部族の神話では、「虹蛇」が、大地を作り、魚を作り、精霊達を生みました。
部族によっては、「虹蛇」は、成人イニシエーションで、人を飲み込み、吐き出します。
部族によっては、儀礼やうなり板などをもたらした存在でもあります。
ちなみに、アボリジニは、人間のヘソの奥に「虹蛇」が眠っていて、額からその力を放つと「強力な眼」と呼ばれます。
この肉体内の「虹蛇」は、インドのクンダリニーと同じでしょう。
アボリジニ文化には、南インドとのつながりがあります。
<宇宙像と死生観>
アボリジニの至高の神々は、東部などでは、「天空の勇者たち」、「万物の父」などと呼ばれる存在です。
天空は石英に満ち、この「天空の父」の口にも石英が満ちています。
アランダ族の神話によれば、この神は「偉大な父(クンガリチャ)」と呼ばれます。
この神は至高神的存在ですが、人間に無関心、地上や文化などの創造とほとんど無関係な存在です。
ですが、部族によっては、「天空の父」が地形や人間を作ったとする場合もあります。
一方、北部などの諸部族では、「多産なる母」、「万物の母」などと呼ばれる存在の信仰があります。
アボリジニは、「割れ目のある水晶(虹が生じる水晶)」が創造の起原となる存在であると考えます。
これは「天空にある水晶の玉座」とも表現されます。
その「透明な水晶」の部分は、「万物の父」です。
それから生まれる「虹」は、「万物の母」であり、「虹蛇」であり、諸々の先祖を生む存在であす。
・天空の父:水晶
・万物の母:虹
アボリジニの世界観によれば、3つの世界があります。
そして、人間の魂は、それぞれに対応する3つの部分からなります。
・死者の世界 :天空 :男性原理
・まだ生まれていない者の世界:水溜り等:男性原理
・生者と死につつある者の世界:地上 :女性原理
「死者の国」は、天上の星団(天空の水溜り)にあります。
死者は、「霊的なカヌー」に乗って、「死者の島」を経て、「死者の国」に至ります。
人間の魂の循環は、水の循環(天・雨・水場)と重ねられます。
「男性原理」は、「死の原理」であり、肉体では「精子」に象徴されます。
後述するように、長老は、多段階のイニシエーションを経て、天空の世界に一体化していきます。
<ドリームタイムとドリーミング>
アボリジニは、神話的時代を「ドリームタイム」と呼びます。
「原初の時」、「昔々」という意味ですが、「物語」という意味もあります。
ですが、「ドリームタイム」は、現在でも存在して働いているので、「あの世(根の国)」といった意味合いもあります。
また、それが地上に現れることも意味します。
「ドリームタイム」とほとんど類似した言葉に「ドリーミング」があります。
「ドリーミング」は、そこにいる「トーテム先祖」を意味します。
また、「トーテム先祖」が生んだ「霊的子供」は、「受胎ドリーミング」と呼ばれます。
さらには、「ドリーミング」は、これらに関する信仰をも意味します。
ただ、「ドリームタイム」はオーストラリアの人類学者の翻訳であって、原語では、例えば、有名なアランダ族の場合は「アルチェリンガ」です。
「ドリームタイム」は、地上世界(日常の認識世界)を作っている基盤となる世界です。
地上の形態を形成する創造力であり、その原型です。
「ドリームタイム」の世界は、大地の中に種や根があるようなイメージで捉えることができます。
この「種」は、一種の「イデア」、「元型」のような存在です。
これはワルビリ族の言葉では、「グルワリ(トーテムデザイン)」と呼ばれます。
「ドリームタイム」から地上世界が生まれることは、内的・心的・潜在的なものが、外的・物質的・具体的なものになるという創造のプロセスです。
あるアボリジニは、白人に対して、人間や動物は「ドリームタイム」の「トーテム先祖」の写真(つまり、写像)なのだと、説明しました。
アボリジニの「ドリームタイム」と地上の関係は、日本語の「根の国(常世)」と「現世(ウツシヨ」の関係と同じです。
アボリジニは、日常で現実のカンガルーを見ている時も、常にその背後にある、カンガルーを形作っている潜在的な力である「ドリームタイム」のカンガルーを感じています。
これはプロセス指向心理学が言う「24時間の明晰夢」と似ています。
意識的な言葉やイメージの背景にある、直観的、フィーリング的なものに注意をしているのでしょう。
<高位イニシエーション>
アボリジニの社会では、男性も女性も、死ぬまで多数のイニシエーションを行います。
ある部族の男性には、十数段階のイニシエーションがあって、それらを通過することで高位の長老になります。
擬死を体験するイニシエーションを体験するごとに、「死」の世界、つまり、「ドリームタイム」の世界、潜在意識の世界に、自己の意識を深めていくのです。
最初の成人イニシエーションでは、夢を見ながらそれを自覚する覚醒夢の見方や、ダンスによってトランス状態に入ることも学びます。
男性は、成人のイニシエーションでは、世界の他の地域でも見られるように、男性器の包皮切開を行います。
ですが、これに続くイニシエーションでは、尿道切開を行う場合があります。
これは、女性のように小便を放つようになるため、つまり、両性具有的存在になるためのものです。
また、イニシエーションで、他にも肉体を傷つけることがありますが、これは、「ドリームタイム」のエネルギーの象徴であり、先祖とのつながりの証となります。
女性の成人イニシエーションでは、水の中に沈められる体験をします。
これは世界の他の地域でも見られるもので、浄化の儀礼とも考えられますが、ひょっとしたら、アボリジニにおいては「虹蛇」や「霊的子供」と関係するのかもしれません。
成人した女性には、体を赤く塗ったり、白い三日月を描いたりすることもあります。
これは、月経を月から受ける存在になったことを示します。
アボリジニの社会では、先祖とのコミュニケーションは、高位の長老が担います。
高位イニシエーションは、天空の英雄とトーテム先祖が司ります。
高位イニシエーションは、天空、地上、地下の3つの領域を自由に往来できることを目指します。
高位の長老になることは、天空のエネルギーと一体になることです。
死に臨んだ長老は、青空を眺めて、そこに見える光の粒子と一体化する瞑想を行います。
アボリジニでは、死者が生前にどの位階まで進んだかによって、その人間の埋葬法が変わります。
高位イニシエーションでは、水晶を体に埋め込まれたり、後頭部から脳中枢に槍を突き刺されたりといった体験をすることがあります。
実際に、例えば舌に水晶を埋め込む場合もあります。
高位の長老は、トランス状態で、糸が絡み合ってできた網と、そこに夢やビジョンがぶら下がっているのを見ます。
ですが、恐れがあると、それらが見えなくなります。
また、アボリジニが、狩猟民から牧畜民に変化すると、やはり霊視の力を失うそうです。
アボリジニの社会は、男性も女性も多段階のイニシエーションを備えていて、「ドリーミタイム」と呼ばれる霊的次元に深く同調するように、生涯をかけてその成長を目指します。
アボリジニの文化は人類の原型的な文化ですが、精神的な側面では完成された文化でしょう。
<トーテム先祖の創世神話>
アボリジニの文化は、トーテミズムの特徴を持っています。
「トーテム先祖」は、特定の氏族の先祖であり、特定の動物や植物、天体、自然などの先祖でもあり、両者の魂がそこに帰り、そこから生まれる存在です。
「トーテム先祖」は、神話の時代に人間の姿になったり、動物の姿になったりしましたが、その性質は、人間には内面に、動物には外面に与えられます。
ただ、アボリジニには、この氏族のトーテム以外にも、性別(母系半族、父系半族)に関わるトーテムと、「パワー・アニマル(守護霊)」としての個人のトーテムがあります。
また、アボリジニにおいては、トーテムは、人間を動物だけでなく、土地と強く結びついています。
アボリジニの神話では、「トーテム先祖」のは、多くは地下から現れて(一部は天から)、長い旅をし、地形を作り、聖地を作り、名づけを行い、法(タブー)と儀礼をもたらしました。
そして、人間と動物を生み、また、「霊的子供」を生みました。
「霊的子供」は、水場などにいて、近くを訪れた女性の中に直接入ったり、男性が狩る動物の中に入って食されることで女性の中に入ったりして、人間の赤ん坊として生まれます。
「トーテム先祖」が旅した道は、「ソングライン」とも呼ばれ、これに沿って歩いて狩りを行います。
また、この道は交易のネットワークにもなりました。
聖地を多くは、井戸や泉などの水場であり、そこは人間が生まれ、死者が一旦戻って行く場所です。
また、聖地は、動・植物を殺さないタブーの場所でもあります。
アランダ族の神話では、原初に、水溜りに胎児のような原人間達が、つながった状態で存在しました。
また、「トーテム先祖」が大地の下で眠っていました。
「ドリームタイム」が始まると、この原人間は、大地から生まれて、放浪して大地を形作りました。
そして、「トーテム先祖」がこの原人間を引き離して、口・目・鼻を開けました。
こうして人間が誕生しましたが、最初の人間達は文化を作って英雄になりました。
また、「トーテム先祖」は、その歩んだところどころに「霊的子供」を残しました。
「トーテム先祖」は地下へ帰りましたが、彼らが地上で誕生した地と帰還した地は、祭儀の場所となりました。
アボリジニが持っている「チュリンガ」という祭儀は、この「トーテム祖先」の通った道や宿の場所が表現されています。
別の「トーテム先祖」の神話では、眠っている「トーテム先祖」の体にトーテム動物達が入ったり、体からトーテム動物達が生まれたりします。
そして、人間は、「トーテム先祖」の脇の下から生まれます。
また、「トーテム先祖」が「チュリンガ」になり、その中に「霊的子供」がいます。
このように、「トーテム先祖」は、各氏族にとっての霊魂、文化、大地の環境の創造力そのものであり、その原型的存在です。
<虹蛇>
北部、中央部など各地の諸部族は、様々な名前で呼ばれる「虹蛇」を信仰しています。
「虹蛇」は、生命を与える水の化身であり、創造と豊穣、霊魂の根源的存在です。
「虹蛇」は、両性具有的存在ですが、その外的形態は男性(男根)であり、内部は女性であるとも考えられています。
また、水晶との対比した場合には女性原理とされます。
「虹蛇」は、大地と宇宙のエネルギーであり、池の底に住み、大地と天空を結びます。
「ドリームタイム」には、雨を司って、洪水をもたらしました。
クンウィンジク族の神話によれば、原初の創造的存在である「インガルナ」が「虹蛇」を生み、「虹蛇」が万物を生みました。
ある部族の神話では、「虹蛇」から生まれた口のない原人間が、大地を作り、「霊的子供」を残して、「虹蛇」に戻りました。
また、ある部族の神話では、「虹蛇」が、大地を作り、魚を作り、精霊達を生みました。
部族によっては、「虹蛇」は、成人イニシエーションで、人を飲み込み、吐き出します。
部族によっては、儀礼やうなり板などをもたらした存在でもあります。
ちなみに、アボリジニは、人間のヘソの奥に「虹蛇」が眠っていて、額からその力を放つと「強力な眼」と呼ばれます。
この肉体内の「虹蛇」は、インドのクンダリニーと同じでしょう。
アボリジニ文化には、南インドとのつながりがあります。
<宇宙像と死生観>
アボリジニの至高の神々は、東部などでは、「天空の勇者たち」、「万物の父」などと呼ばれる存在です。
天空は石英に満ち、この「天空の父」の口にも石英が満ちています。
アランダ族の神話によれば、この神は「偉大な父(クンガリチャ)」と呼ばれます。
この神は至高神的存在ですが、人間に無関心、地上や文化などの創造とほとんど無関係な存在です。
ですが、部族によっては、「天空の父」が地形や人間を作ったとする場合もあります。
一方、北部などの諸部族では、「多産なる母」、「万物の母」などと呼ばれる存在の信仰があります。
アボリジニは、「割れ目のある水晶(虹が生じる水晶)」が創造の起原となる存在であると考えます。
これは「天空にある水晶の玉座」とも表現されます。
その「透明な水晶」の部分は、「万物の父」です。
それから生まれる「虹」は、「万物の母」であり、「虹蛇」であり、諸々の先祖を生む存在であす。
・天空の父:水晶
・万物の母:虹
アボリジニの世界観によれば、3つの世界があります。
そして、人間の魂は、それぞれに対応する3つの部分からなります。
・死者の世界 :天空 :男性原理
・まだ生まれていない者の世界:水溜り等:男性原理
・生者と死につつある者の世界:地上 :女性原理
「死者の国」は、天上の星団(天空の水溜り)にあります。
死者は、「霊的なカヌー」に乗って、「死者の島」を経て、「死者の国」に至ります。
人間の魂の循環は、水の循環(天・雨・水場)と重ねられます。
「男性原理」は、「死の原理」であり、肉体では「精子」に象徴されます。
後述するように、長老は、多段階のイニシエーションを経て、天空の世界に一体化していきます。
<ドリームタイムとドリーミング>
アボリジニは、神話的時代を「ドリームタイム」と呼びます。
「原初の時」、「昔々」という意味ですが、「物語」という意味もあります。
ですが、「ドリームタイム」は、現在でも存在して働いているので、「あの世(根の国)」といった意味合いもあります。
また、それが地上に現れることも意味します。
「ドリームタイム」とほとんど類似した言葉に「ドリーミング」があります。
「ドリーミング」は、そこにいる「トーテム先祖」を意味します。
また、「トーテム先祖」が生んだ「霊的子供」は、「受胎ドリーミング」と呼ばれます。
さらには、「ドリーミング」は、これらに関する信仰をも意味します。
ただ、「ドリームタイム」はオーストラリアの人類学者の翻訳であって、原語では、例えば、有名なアランダ族の場合は「アルチェリンガ」です。
「ドリームタイム」は、地上世界(日常の認識世界)を作っている基盤となる世界です。
地上の形態を形成する創造力であり、その原型です。
「ドリームタイム」の世界は、大地の中に種や根があるようなイメージで捉えることができます。
この「種」は、一種の「イデア」、「元型」のような存在です。
これはワルビリ族の言葉では、「グルワリ(トーテムデザイン)」と呼ばれます。
「ドリームタイム」から地上世界が生まれることは、内的・心的・潜在的なものが、外的・物質的・具体的なものになるという創造のプロセスです。
あるアボリジニは、白人に対して、人間や動物は「ドリームタイム」の「トーテム先祖」の写真(つまり、写像)なのだと、説明しました。
アボリジニの「ドリームタイム」と地上の関係は、日本語の「根の国(常世)」と「現世(ウツシヨ」の関係と同じです。
アボリジニは、日常で現実のカンガルーを見ている時も、常にその背後にある、カンガルーを形作っている潜在的な力である「ドリームタイム」のカンガルーを感じています。
これはプロセス指向心理学が言う「24時間の明晰夢」と似ています。
意識的な言葉やイメージの背景にある、直観的、フィーリング的なものに注意をしているのでしょう。
<高位イニシエーション>
アボリジニの社会では、男性も女性も、死ぬまで多数のイニシエーションを行います。
ある部族の男性には、十数段階のイニシエーションがあって、それらを通過することで高位の長老になります。
擬死を体験するイニシエーションを体験するごとに、「死」の世界、つまり、「ドリームタイム」の世界、潜在意識の世界に、自己の意識を深めていくのです。
最初の成人イニシエーションでは、夢を見ながらそれを自覚する覚醒夢の見方や、ダンスによってトランス状態に入ることも学びます。
男性は、成人のイニシエーションでは、世界の他の地域でも見られるように、男性器の包皮切開を行います。
ですが、これに続くイニシエーションでは、尿道切開を行う場合があります。
これは、女性のように小便を放つようになるため、つまり、両性具有的存在になるためのものです。
また、イニシエーションで、他にも肉体を傷つけることがありますが、これは、「ドリームタイム」のエネルギーの象徴であり、先祖とのつながりの証となります。
女性の成人イニシエーションでは、水の中に沈められる体験をします。
これは世界の他の地域でも見られるもので、浄化の儀礼とも考えられますが、ひょっとしたら、アボリジニにおいては「虹蛇」や「霊的子供」と関係するのかもしれません。
成人した女性には、体を赤く塗ったり、白い三日月を描いたりすることもあります。
これは、月経を月から受ける存在になったことを示します。
アボリジニの社会では、先祖とのコミュニケーションは、高位の長老が担います。
高位イニシエーションは、天空の英雄とトーテム先祖が司ります。
高位イニシエーションは、天空、地上、地下の3つの領域を自由に往来できることを目指します。
高位の長老になることは、天空のエネルギーと一体になることです。
死に臨んだ長老は、青空を眺めて、そこに見える光の粒子と一体化する瞑想を行います。
アボリジニでは、死者が生前にどの位階まで進んだかによって、その人間の埋葬法が変わります。
高位イニシエーションでは、水晶を体に埋め込まれたり、後頭部から脳中枢に槍を突き刺されたりといった体験をすることがあります。
実際に、例えば舌に水晶を埋め込む場合もあります。
高位の長老は、トランス状態で、糸が絡み合ってできた網と、そこに夢やビジョンがぶら下がっているのを見ます。
ですが、恐れがあると、それらが見えなくなります。
また、アボリジニが、狩猟民から牧畜民に変化すると、やはり霊視の力を失うそうです。
沖縄の池間島のコスモロジー [伝統文化のコスモロジー]
沖縄の池間島には、典型的なシャーマン的コスモロジーが伝えられています。
これは沖縄地方のコスモロジーの典型ではありませんが、驚くほどよくできた、素晴らしいコスモロジーです。
松居友「沖縄の宇宙像」を参照してこれを簡単に紹介します。
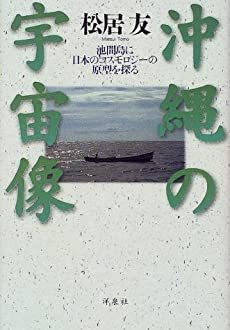
<沖縄・久高島の宗教文化の成り立ち>
その前に、沖縄地方の久高島の宗教文化の成り立ちについて概説します。
久高島は、琉球列島の中央に位置し、近年に至るまで豊富な儀礼を残し、その研究もされてきました。
そのため、沖縄地方の典型的な宗教文化の成り立ちを知るために適しているのです。
久高島の宗教・儀礼は次のような3種類に分類できます。
この島の、そして、沖縄の宗教文化は、こういった複数の文化が複合したものだと言えます。
(祭祀者) (祭神)
1 ソールイ :竜宮神
2 ムトゥガミ:ニライカナイのムトゥ神
3 ノロ :天上の祖神
1は、漁撈を行う男性の年齢階梯結社である「ソールイ(ソールイガナシー)」が、主に海底他界と考えられる竜宮の神を祀ります。
この神は、漁撈の神であり、蛇神です。
彼らは、竜宮(外洋)からの来訪神(マレビト)の祭祀を行います。
この祭祀は、八重山諸島のアカマタ・クロマタ祭祀などと同類のものです。
これらは、先オーストロネシア的な地中から始祖が出現したとする神話を持ち、芋類などの根菜栽培を行う、東南アジア系の文化であると考えられます。
2は、「ムトゥガミ」という男女の神職が、海上他界で死者の世界でもある「ニラーハラー(ニライカナイ)」の神「ムトゥ」を祀ります。
彼らは、「ニラーハラー」から来訪する「アカハンジャナシー」の祭祀を行います。
「ムトゥ」は「始祖家」という意味で、「ムトゥ」神は、島の創世の始祖神です。
この神は、兄・妹(あるいは夫婦)の2人の神で、氏族を守ります。
来訪神は神女(タマガエー)に憑依しますが、彼女達は、沖縄地方で「ユタ」と呼ばれる霊媒(憑依型シャーマン)です。
この祭祀は、沖縄本島の海神ウンジャミの祭祀と同類のものと考えられます。
これらは、海上他界と蛇霊信仰を持ち、漁撈を行う、南中国系の文化であると考えられます。
3は、女性神職の「ノロ」が、御嶽(ウタキ:沖縄の神社)で、天の神と、祖母霊を祀ります。
天の神は、沖縄地方では一般に「オボツ」の神と呼ばれ、一人の男性神、もしくは、7人の神とされます。
「ノロ」は、死後、「ニラーハラー」の神の承認を受けて、御嶽に守護霊として戻ると考えられています。
祖母霊というのは、先代のノロの霊です。
これらは、天の神が地上の聖地に常住する信仰を持ち、麦作を行う、北方系の文化であると考えられます。
「ノロ」の制度は、琉球王朝によって5世紀ほど前にもたらしたもので、階層的な組織になっています。
「ノロ」は、本島から派遣された「外間ノロ」が仕切り、島の祭祀を担います。
島のすべての主婦は、30-41歳になると「イザイホー」という儀式を経て女性神職である「神女(タマガエー)」になり、やがて「ノロ」に参加(池間ノロ)します。
主婦であるノロは、祖母の霊を祀り、家庭の祭祀を担います。
それとは別に、若くしてシャーマン病のような状態になった女性は、ユタの判断で、「ムトゥガミ」になり、氏族の祭祀を担います。
また、沖縄には、「オナリ信仰」というのがあって、これは妹が兄を守護するとする信仰です。
上記の3者の間では、「ノロ」が「ソールイ」の守護霊となるという関係で、「オナリ信仰」が表現されています。
*この項、主に吉成直樹「マレビトの文化史」を参照
<池間島の宇宙像>
池間島は、宮古島の北西にあるごく小さな島です。
この島の宗教文化も、上記のように複数の文化の複合を経験しているハズですが、それらが見事に統合されたシャーマン的な宇宙像を持っています。
世界は「天上」、中の国である「地上」、「ニッラ(ニライカナイ)」と呼ばれる祖霊(マウカン)のいる根の国である「地下」(地上と逆さまな世界)の3つからなります。
池間島の人々は北方シャーマニズムと同じく7を聖数にしていたためか、天球は7層で構成されています。
上から、太陽/月/北極星/オリオン座の3つ星/北斗七星/サソリ座/南斗六星に対応する天球です。
それぞれの天体が神でもあって、この7神が御嶽に祭られます。
(池間島の宇宙像)
天上
・太陽の男神
・月の女神
・北極星の女神ネノハンマティダ :中央
・オリオン座3つ星の男神ナイカニ :東
・北斗七星(天への舟)ウトゥユンバジュルク:北
・サソリ座の火の神ミサダメ :西
・南斗六星の蛇神(ニッラへの舟)バカバウ :南
---------
地上(中の国)
・中央の柱ナカドゥラ神
---------
ニッラ(根の国)
・南極星の男神ウマノハノユーヌヌス
太陽神は男神で、月神は女性です。
両神は常に天を巡り、地上にはやってこないので、御嶽には座がありません。
池間島は地上の中心であり、北極星の間には軸があって、これを中心に天球と地が回ります。
オリオン、北斗、サソリ座、南斗はそれぞれ東、北、西、南に対応します。
天に昇って北極星の穴を抜けて天上に上がると、山や湖があって北極星の女神「ネノハンマティダ」がいます。
湖の水は生命の水で、女神は生命の水の女神でもあるのです。
北極星の女神は地上の生命の生死を司る最高神的存在です。
地上の御嶽には北極星の使者の神(小熊座?)がいます。
北斗七星は霊魂を天に運ぶ舟です。
北斗は北から東を回って天に昇ります。
この舟は、地上⇔北⇔東⇔天上 の間を航海します。
東を示すオリオンの3つ星は男神で、天への登り口である東を示します。
オリオンの3つ星は航海の神ですが、これは天上への航海でもあるのです。
天に昇る霊魂は北斗に乗って東から昇り、天の川を進みます。
西のサソリ座の神は火の神で、人の行ないを監視して天の神に報告する神です。
そして、ニッラへの降り口を示します。
南斗は生命力を与える蛇の神です。
そして、地下の国と地上を結ぶ舟でもあり、南極星の使者です。
この舟は、地上⇔西⇔南⇔ニッラ の間を航海します。
ニッラには男神である南極星の神「ウマノハノユーヌヌス」がいます。
この神はユーと呼ばれる生命力を地上に与えます。
ニッラは汚れた場所ではなく、生命力の基盤である「根の国」なのです。
ニッラには、西の水平線からではなく、海岸の洞窟などから降りていくこともできます。
<池間島の死生観>
人が誕生した時には、東にある井戸の水を浴びせ、亡くなった時は、西にある井戸の水を浴びせます。
一般の人は、死後、地下のニッラに行きます。
ニッラは祖霊がいる場所です。
墓は、死者にとってニッラに行くまでの仮の家とされます。
死者は、墓と生活空間を行き来しますが、この期間は、いわゆる殯(もがり)の期間で9日間です。
その期間が終わると、洗骨をし、骨は「祖先墓」に移されます。
そして、ニッラに行きますが、3ヶ月の移行期間は行き来をします。
その後に、祖霊となります。
ですが、一般の人と違って、シャーマンや王族のような一部の人間は、死後、天に行きます。
<池間島の祭儀>
池間島の大きな祭は、正月に相当する「サウガツ」、盆・収穫祭に相当する「ミャークヅツ」、立冬祭に相当する「ユークイ」です。
年末には祖霊や地下、地上(御嶽)の神々が天上に集まります。
この時、地上の人々の行ないが報告され、祖霊は人間の弁護をします。
これは、本土の神々が出雲に集う「神無月」に相当するでしょう。
本土の神々は出雲から西方の「常世」に行くのでしょう。
次に、元旦に天の神々によって1年の計画が決められ、7日にはその計画表を地上の神が持って戻ります。
次に、満月の15日の小正月には、地上に戻った祖神が、地上を訪れるので、感謝します。
これに対して、盆には天の神々や祖霊が地上に集まります。
そして、太陽神に収穫物が捧げられ、感謝されます。
立冬祭の「ユークイ」は太陽神の力を呼び戻し、来年の豊作を祈願する祭です。
シャーマン的な巫女である神女達の祈願によって、まず、南極星の男神が祖霊と共に生命力を持って南斗の舟で地上にやってきます。
本土で言う七福神の乗る「宝舟」です。
次に、南極星の男神や祖霊、そしてシャーマンのように脱魂した神女達は北斗の舟に乗り換えて天上にまで昇ります。
そして、太陽神と向かい合い、南極星の男神と北極星の女神は聖婚を行ないます。
これによって太陽神が喜び、復活します。
次に、南極星の男神や祖霊はニッラにまで戻って、生命力ユーを本格的に目覚めさせます。そして再度、地上にそれらをもたらしにやってきます。
*池間島の部分は、松居友「沖縄の宇宙像」を参照
これは沖縄地方のコスモロジーの典型ではありませんが、驚くほどよくできた、素晴らしいコスモロジーです。
松居友「沖縄の宇宙像」を参照してこれを簡単に紹介します。
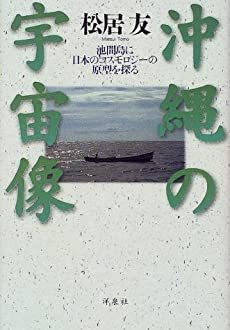
<沖縄・久高島の宗教文化の成り立ち>
その前に、沖縄地方の久高島の宗教文化の成り立ちについて概説します。
久高島は、琉球列島の中央に位置し、近年に至るまで豊富な儀礼を残し、その研究もされてきました。
そのため、沖縄地方の典型的な宗教文化の成り立ちを知るために適しているのです。
久高島の宗教・儀礼は次のような3種類に分類できます。
この島の、そして、沖縄の宗教文化は、こういった複数の文化が複合したものだと言えます。
(祭祀者) (祭神)
1 ソールイ :竜宮神
2 ムトゥガミ:ニライカナイのムトゥ神
3 ノロ :天上の祖神
1は、漁撈を行う男性の年齢階梯結社である「ソールイ(ソールイガナシー)」が、主に海底他界と考えられる竜宮の神を祀ります。
この神は、漁撈の神であり、蛇神です。
彼らは、竜宮(外洋)からの来訪神(マレビト)の祭祀を行います。
この祭祀は、八重山諸島のアカマタ・クロマタ祭祀などと同類のものです。
これらは、先オーストロネシア的な地中から始祖が出現したとする神話を持ち、芋類などの根菜栽培を行う、東南アジア系の文化であると考えられます。
2は、「ムトゥガミ」という男女の神職が、海上他界で死者の世界でもある「ニラーハラー(ニライカナイ)」の神「ムトゥ」を祀ります。
彼らは、「ニラーハラー」から来訪する「アカハンジャナシー」の祭祀を行います。
「ムトゥ」は「始祖家」という意味で、「ムトゥ」神は、島の創世の始祖神です。
この神は、兄・妹(あるいは夫婦)の2人の神で、氏族を守ります。
来訪神は神女(タマガエー)に憑依しますが、彼女達は、沖縄地方で「ユタ」と呼ばれる霊媒(憑依型シャーマン)です。
この祭祀は、沖縄本島の海神ウンジャミの祭祀と同類のものと考えられます。
これらは、海上他界と蛇霊信仰を持ち、漁撈を行う、南中国系の文化であると考えられます。
3は、女性神職の「ノロ」が、御嶽(ウタキ:沖縄の神社)で、天の神と、祖母霊を祀ります。
天の神は、沖縄地方では一般に「オボツ」の神と呼ばれ、一人の男性神、もしくは、7人の神とされます。
「ノロ」は、死後、「ニラーハラー」の神の承認を受けて、御嶽に守護霊として戻ると考えられています。
祖母霊というのは、先代のノロの霊です。
これらは、天の神が地上の聖地に常住する信仰を持ち、麦作を行う、北方系の文化であると考えられます。
「ノロ」の制度は、琉球王朝によって5世紀ほど前にもたらしたもので、階層的な組織になっています。
「ノロ」は、本島から派遣された「外間ノロ」が仕切り、島の祭祀を担います。
島のすべての主婦は、30-41歳になると「イザイホー」という儀式を経て女性神職である「神女(タマガエー)」になり、やがて「ノロ」に参加(池間ノロ)します。
主婦であるノロは、祖母の霊を祀り、家庭の祭祀を担います。
それとは別に、若くしてシャーマン病のような状態になった女性は、ユタの判断で、「ムトゥガミ」になり、氏族の祭祀を担います。
また、沖縄には、「オナリ信仰」というのがあって、これは妹が兄を守護するとする信仰です。
上記の3者の間では、「ノロ」が「ソールイ」の守護霊となるという関係で、「オナリ信仰」が表現されています。
*この項、主に吉成直樹「マレビトの文化史」を参照
<池間島の宇宙像>
池間島は、宮古島の北西にあるごく小さな島です。
この島の宗教文化も、上記のように複数の文化の複合を経験しているハズですが、それらが見事に統合されたシャーマン的な宇宙像を持っています。
世界は「天上」、中の国である「地上」、「ニッラ(ニライカナイ)」と呼ばれる祖霊(マウカン)のいる根の国である「地下」(地上と逆さまな世界)の3つからなります。
池間島の人々は北方シャーマニズムと同じく7を聖数にしていたためか、天球は7層で構成されています。
上から、太陽/月/北極星/オリオン座の3つ星/北斗七星/サソリ座/南斗六星に対応する天球です。
それぞれの天体が神でもあって、この7神が御嶽に祭られます。
(池間島の宇宙像)
天上
・太陽の男神
・月の女神
・北極星の女神ネノハンマティダ :中央
・オリオン座3つ星の男神ナイカニ :東
・北斗七星(天への舟)ウトゥユンバジュルク:北
・サソリ座の火の神ミサダメ :西
・南斗六星の蛇神(ニッラへの舟)バカバウ :南
---------
地上(中の国)
・中央の柱ナカドゥラ神
---------
ニッラ(根の国)
・南極星の男神ウマノハノユーヌヌス
太陽神は男神で、月神は女性です。
両神は常に天を巡り、地上にはやってこないので、御嶽には座がありません。
池間島は地上の中心であり、北極星の間には軸があって、これを中心に天球と地が回ります。
オリオン、北斗、サソリ座、南斗はそれぞれ東、北、西、南に対応します。
天に昇って北極星の穴を抜けて天上に上がると、山や湖があって北極星の女神「ネノハンマティダ」がいます。
湖の水は生命の水で、女神は生命の水の女神でもあるのです。
北極星の女神は地上の生命の生死を司る最高神的存在です。
地上の御嶽には北極星の使者の神(小熊座?)がいます。
北斗七星は霊魂を天に運ぶ舟です。
北斗は北から東を回って天に昇ります。
この舟は、地上⇔北⇔東⇔天上 の間を航海します。
東を示すオリオンの3つ星は男神で、天への登り口である東を示します。
オリオンの3つ星は航海の神ですが、これは天上への航海でもあるのです。
天に昇る霊魂は北斗に乗って東から昇り、天の川を進みます。
西のサソリ座の神は火の神で、人の行ないを監視して天の神に報告する神です。
そして、ニッラへの降り口を示します。
南斗は生命力を与える蛇の神です。
そして、地下の国と地上を結ぶ舟でもあり、南極星の使者です。
この舟は、地上⇔西⇔南⇔ニッラ の間を航海します。
ニッラには男神である南極星の神「ウマノハノユーヌヌス」がいます。
この神はユーと呼ばれる生命力を地上に与えます。
ニッラは汚れた場所ではなく、生命力の基盤である「根の国」なのです。
ニッラには、西の水平線からではなく、海岸の洞窟などから降りていくこともできます。
<池間島の死生観>
人が誕生した時には、東にある井戸の水を浴びせ、亡くなった時は、西にある井戸の水を浴びせます。
一般の人は、死後、地下のニッラに行きます。
ニッラは祖霊がいる場所です。
墓は、死者にとってニッラに行くまでの仮の家とされます。
死者は、墓と生活空間を行き来しますが、この期間は、いわゆる殯(もがり)の期間で9日間です。
その期間が終わると、洗骨をし、骨は「祖先墓」に移されます。
そして、ニッラに行きますが、3ヶ月の移行期間は行き来をします。
その後に、祖霊となります。
ですが、一般の人と違って、シャーマンや王族のような一部の人間は、死後、天に行きます。
<池間島の祭儀>
池間島の大きな祭は、正月に相当する「サウガツ」、盆・収穫祭に相当する「ミャークヅツ」、立冬祭に相当する「ユークイ」です。
年末には祖霊や地下、地上(御嶽)の神々が天上に集まります。
この時、地上の人々の行ないが報告され、祖霊は人間の弁護をします。
これは、本土の神々が出雲に集う「神無月」に相当するでしょう。
本土の神々は出雲から西方の「常世」に行くのでしょう。
次に、元旦に天の神々によって1年の計画が決められ、7日にはその計画表を地上の神が持って戻ります。
次に、満月の15日の小正月には、地上に戻った祖神が、地上を訪れるので、感謝します。
これに対して、盆には天の神々や祖霊が地上に集まります。
そして、太陽神に収穫物が捧げられ、感謝されます。
立冬祭の「ユークイ」は太陽神の力を呼び戻し、来年の豊作を祈願する祭です。
シャーマン的な巫女である神女達の祈願によって、まず、南極星の男神が祖霊と共に生命力を持って南斗の舟で地上にやってきます。
本土で言う七福神の乗る「宝舟」です。
次に、南極星の男神や祖霊、そしてシャーマンのように脱魂した神女達は北斗の舟に乗り換えて天上にまで昇ります。
そして、太陽神と向かい合い、南極星の男神と北極星の女神は聖婚を行ないます。
これによって太陽神が喜び、復活します。
次に、南極星の男神や祖霊はニッラにまで戻って、生命力ユーを本格的に目覚めさせます。そして再度、地上にそれらをもたらしにやってきます。
*池間島の部分は、松居友「沖縄の宇宙像」を参照
秘密結社と多段階イニシエーション [伝統文化のコスモロジー]
伝統的な部族社会で霊的な活動を担うのは、主にシャーマンか秘密結社のリーダー達、場合によっては、長老的存在です。
秘密結社のリーダ達やある種の長老になるためには、多段階のイニシエーションを通過する必要がある社会もあります。
<秘密結社>
世界の地域によって、霊的な活動を主にシャーマンが担う社会と、多数の秘密結社が担う社会があります。
例えば、西アフリカでは、多数の秘密結社が存在します。
ただ、すべての秘密結社が霊的な知識や技術を持つとは限りません。
多くの部族文化には秘密結社が存在し、それはごくありふれた存在です。
多数の秘密結社がある社会では、誰もが複数の結社に属します。
秘密結社の目的は、社会の中での特定の役割を果たすことであり、また、そのためにメンバーを守ることです。
秘密結社は、メンバー外の人間には、その活動、知識などを秘密にします。
メンバーそのものを秘密にする場合もあります。
狭義の「秘密結社」は、この意味の結社かもしれません。
また、秘密結社とそうでない集団には厳密な区別がない場合もあります。
その結社のメンバーを回りの者が知っていても、知らないふりをする社会もあります。
秘密結社の主な種類には、年齢的集団や職業集団、儀礼集団などがあります。
秘密結社には、歳をとって成長するにしたがって誰もが加入するタイプの集団と、自分の意志で加入するタイプの集団があります。
秘密結社には、同性で同年齢(あるいは近い年齢)の集団である「年齢集団」があります。
これには子供や成人、長老のように、もう少し幅の広い年齢的集団もあります。
父親や母親のような家族の役割に関わる結社もあります。
「長老集団」は部族の最高会議を構成しています。
長老達は多くの知識を持っていますが、相手が倫理的、知的に十分な資質を持っているかを慎重に判断してからしか何も教えません。
また、それぞれの職業に応じた「職業集団」があります。
特に「狩猟者」と「鍛冶屋」の集団は、見えない力をコントロールできる高い力を持っていると考えられて、尊敬されると共に恐れられました。
これら以外にも様々な儀式を司るような「秘密結社」と呼ばれる集団があります。
来訪神の儀礼、葬儀の儀礼、特別なイニシエーション儀礼などの集団です。
日本では、秋田のナマハゲや沖縄のアカマタ・クロマタのような来訪神の儀礼は、本来は秘密結社が担っていたものです。
米北西部のインディアンで有名な「アザラシ結社」が冬に行うイニシエーション儀礼は、「人食い怪物」に食べられる擬死再生儀礼で、これによって「人食い怪物」の性質を持った立派な人間になると考えます。
別のページで書いたように、これは夏に人間が動物を狩猟して食べて冥界に送ることと、ちょうど対称的です。
<秘密結社の社会の多重構造>
多数の秘密結社を持つ社会は、多重な組織構造からできている社会です。
また、社会によっては、昼と夜、光と闇、夏と冬、表と裏といった言葉に象徴されるような、双極的な構造を持った社会があります。
このような社会では、各人はそれぞれの組織に関わる2種のパーソナリティを持ちます。
例えば、北米のクワキウトゥル族など、北米には双極的な文化を持っている部族があって、冬に多数の秘密結社が活動します。
秘密結社にはリーダーがいますが、彼(彼女)は、単に1つの結社のリーダーでしかありません。
誰がリーダーであるかは、部外者には知られていないこともあります。
社会に複数の秘密結社があると、誰もが部族の知識の全体を知ることはできず、また、権力や尊敬を独占することができないようになっているのです。 こういった権力の分散は、部族社会の特徴です。
秘密結社は、イニシエーション(入社式・加入儀礼、入門儀礼)を持っていることが普通です。
中には、多段階の位階とイニシエーショを持っている場合もあります。
位階に応じて、知識や技術が開示され、教育がなされます。
ですが、こういった秘密結社の儀礼や技術についてはほとんど分かっていません。
おそらくアボリジニーがそうであるように、必ずしも秘密結社という形を取らずとも、多段階のイニシエーションを持つ文化もあります。
アボリジニーのある部族では、男性に十数段階のイニシエーションがあります。
「秘密結社」が持つ知識や技術には、物質的なものもあれば、霊的な力をコントロールしたり、特定の精霊や先祖とコミュニケートする能力などがあります。
西アフリカでは、秘密結社は具体的な知識だけでなく、それぞれが固有のダンスや音楽を持っています。
これらは見えない力のコントロールと関係しています。
このような部族の秘密結社のあり方、秘密主義と位階構造は、後の様々な神秘主義の団体に受け継がれました。
秘密結社のリーダ達やある種の長老になるためには、多段階のイニシエーションを通過する必要がある社会もあります。
<秘密結社>
世界の地域によって、霊的な活動を主にシャーマンが担う社会と、多数の秘密結社が担う社会があります。
例えば、西アフリカでは、多数の秘密結社が存在します。
ただ、すべての秘密結社が霊的な知識や技術を持つとは限りません。
多くの部族文化には秘密結社が存在し、それはごくありふれた存在です。
多数の秘密結社がある社会では、誰もが複数の結社に属します。
秘密結社の目的は、社会の中での特定の役割を果たすことであり、また、そのためにメンバーを守ることです。
秘密結社は、メンバー外の人間には、その活動、知識などを秘密にします。
メンバーそのものを秘密にする場合もあります。
狭義の「秘密結社」は、この意味の結社かもしれません。
また、秘密結社とそうでない集団には厳密な区別がない場合もあります。
その結社のメンバーを回りの者が知っていても、知らないふりをする社会もあります。
秘密結社の主な種類には、年齢的集団や職業集団、儀礼集団などがあります。
秘密結社には、歳をとって成長するにしたがって誰もが加入するタイプの集団と、自分の意志で加入するタイプの集団があります。
秘密結社には、同性で同年齢(あるいは近い年齢)の集団である「年齢集団」があります。
これには子供や成人、長老のように、もう少し幅の広い年齢的集団もあります。
父親や母親のような家族の役割に関わる結社もあります。
「長老集団」は部族の最高会議を構成しています。
長老達は多くの知識を持っていますが、相手が倫理的、知的に十分な資質を持っているかを慎重に判断してからしか何も教えません。
また、それぞれの職業に応じた「職業集団」があります。
特に「狩猟者」と「鍛冶屋」の集団は、見えない力をコントロールできる高い力を持っていると考えられて、尊敬されると共に恐れられました。
これら以外にも様々な儀式を司るような「秘密結社」と呼ばれる集団があります。
来訪神の儀礼、葬儀の儀礼、特別なイニシエーション儀礼などの集団です。
日本では、秋田のナマハゲや沖縄のアカマタ・クロマタのような来訪神の儀礼は、本来は秘密結社が担っていたものです。
米北西部のインディアンで有名な「アザラシ結社」が冬に行うイニシエーション儀礼は、「人食い怪物」に食べられる擬死再生儀礼で、これによって「人食い怪物」の性質を持った立派な人間になると考えます。
別のページで書いたように、これは夏に人間が動物を狩猟して食べて冥界に送ることと、ちょうど対称的です。
<秘密結社の社会の多重構造>
多数の秘密結社を持つ社会は、多重な組織構造からできている社会です。
また、社会によっては、昼と夜、光と闇、夏と冬、表と裏といった言葉に象徴されるような、双極的な構造を持った社会があります。
このような社会では、各人はそれぞれの組織に関わる2種のパーソナリティを持ちます。
例えば、北米のクワキウトゥル族など、北米には双極的な文化を持っている部族があって、冬に多数の秘密結社が活動します。
秘密結社にはリーダーがいますが、彼(彼女)は、単に1つの結社のリーダーでしかありません。
誰がリーダーであるかは、部外者には知られていないこともあります。
社会に複数の秘密結社があると、誰もが部族の知識の全体を知ることはできず、また、権力や尊敬を独占することができないようになっているのです。 こういった権力の分散は、部族社会の特徴です。
秘密結社は、イニシエーション(入社式・加入儀礼、入門儀礼)を持っていることが普通です。
中には、多段階の位階とイニシエーショを持っている場合もあります。
位階に応じて、知識や技術が開示され、教育がなされます。
ですが、こういった秘密結社の儀礼や技術についてはほとんど分かっていません。
おそらくアボリジニーがそうであるように、必ずしも秘密結社という形を取らずとも、多段階のイニシエーションを持つ文化もあります。
アボリジニーのある部族では、男性に十数段階のイニシエーションがあります。
「秘密結社」が持つ知識や技術には、物質的なものもあれば、霊的な力をコントロールしたり、特定の精霊や先祖とコミュニケートする能力などがあります。
西アフリカでは、秘密結社は具体的な知識だけでなく、それぞれが固有のダンスや音楽を持っています。
これらは見えない力のコントロールと関係しています。
このような部族の秘密結社のあり方、秘密主義と位階構造は、後の様々な神秘主義の団体に受け継がれました。
ライフサイクルと通過儀礼 [伝統文化のコスモロジー]
<ライフサイクルと通過儀礼>
伝統的な文化では、人間(の魂)を大きなライフサイクル(生命循環)の中で考えます。
この世に誕生し、成長して成人し、成熟して長老になり、亡くなってあの世に行き、個性を脱して祖霊(祖神)になり、子孫を見守り、やがて子孫としてこの世に再生する、というサイクルです。
人(の魂)は、このライフサイクルを歩む中で、いくつもの違った身分(人格・神格)を経ていきます。
その身分を変化させる時々に、「通過儀礼(イニシエーション)」を経ます。
分かりやすい例では、成人式や結婚式、葬式などが「通過儀礼」です。
「通過儀礼」の意味は、古い人格(身分・地位)として死に、新しい人格として再生する「擬死再生」です。
その際に、あるいは、その条件として、必要な知識、能力を身に付けます。
「死」の体験は、様々な演劇的演出によってなされることが多くあります。
幻覚性の薬物を利用する場合もあります。
<4つのプロセス>
ライフサイクルは大きく4つのプロセス(期間)に分けることができます。
① 成長のプロセス :誕生→成人:この世での個別化
② 成熟のプロセス :成人→死 :この世での普遍化
③ 祖神化のプロセス:死→祖神 :あの世での普遍化
④ 祖神としての期間:祖神→誕生:あの世からの個別化
③④は、儀礼を主催するこの世の人間の側から見ると、③が供養、④が先祖祭になります。
ライフサイクルは、「この世(①②)」⇔「あの世(③④)」の循環です。
誕生には「受胎→出産」という中間段階があります。
死にも「葬儀→埋葬」という「中有」とか「もがり」と呼ばれる中間段階があります。
また、ライフサイクルは、「普遍化(②③)」⇔「個別化(④①)」という循環でもあります。
人は誕生後、個性化・個別化して、その極である成人に至ります。
成人した人は、個人を超えて、成熟の道を歩みます。
死は普遍化の道であり、死後の魂もその道を歩み、祖神という普遍化の極に至ります。
そして、祖神の分霊として、再度、個人が再誕します。
各プロセスには、細かくいくつものプロセス(身分と通過儀礼)があります。
少し前の日本の例では…
① 成長のプロセス
誕生(受胎→出産)→名付祝→初宮詣→七五三(子供組加入)→十三参り→成人式(若衆組加入)→結婚・就職
この成人になるには、社会的な知識、合理的な智恵、生活力が必要です。
② 成熟のプロセス
隠居→年祝(還暦→古稀→喜寿→傘寿→米寿…)・年寄(長老)
子供が独立すると隠居になりましたが、これは年齢的にはかなり若い時(40才前くらい)、になります。
他にも、念仏講や庚申講に参加したり、受戒を受けたり、死に備えた段階があります。
成熟には、社会的な調停能力、社会的価値観を相対化する視点、利他精神、無意識の創造力の受容が必要です。
③ 祖神化のプロセス
葬儀(死霊化)→埋葬(精霊化)→年忌法要(祖霊化)→弔い上げ(祖神・氏神化)
祖霊・祖神であれ、浄土に行くホトケであれ、それが普遍的な方向に浄化された魂であることに変わりはありません。
亡くなった人の魂が、悪霊にならずに、この正しい方向に進むようにするのが、葬送と供養の目的です。
水子や幼児の段階で亡くなった場合のように、①②を経ていない魂は、死後に③に進まず、再度、生まれなおすことが望まれます。
④ 祖神の期間
プロセスはありませんが、祖神(祖霊)として子孫を守ります。
祖神(祖霊)は、一般的な氏神の祭り、盆・正月など、定期的にこの世を訪れ、子孫に生命力を与えます。
人はライフサイクルの中で、身分に沿って名前を変えることが一般的でした。
日本人の場合だと、幼名→少年名→家長名→隠居名→戒名・氏神名 といった感じです。
子供には亡くなった祖父母の名を付けることもあります。
独立すると、父から代々の家長としての名を受け継ぎ、父は隠居して祖父から代々の隠居名を受け継ぐ習慣がありました。
<成人儀礼>
成人儀礼の本質は、この世の創造の母体としての他界(=死)と対面して、人格を成長させることでした。
最も原初的な成人儀礼は、洞窟か森の中の儀礼用の小屋で行いました。
洞窟は他界であり、地母神の子宮であり、洞窟から出ることで、新しい人格として再生します。
森も他界であり、小屋は怪物(聖獣)であり、怪物に飲まれ、吐き出されることで再生します。
鯨に飲み込まれたピノキオや、狼に飲み込まれた赤頭巾ちゃんの童話には、原初的な成人式の姿が残っています。
森の中の小屋も、童話の定番です。
他にも、成人儀礼が変形された童話としては、異界に行って、何かを手に入れる(ジャックと豆の木…)とか、何かをやっつける(ヘンデルとグレーテル、一寸法師…)といった形が見られます。
異界に行って戻ることは死と再生の象徴です。
何かを手に入れたり、やっつけたりすることは智恵を獲得する象徴です。
ジブリ作品には成人儀礼の物語が多くあります。
「千と千尋の神隠し」、「となりのトトロ」、「崖の上のポニョ」などは、成女儀礼の物語です。
特に「千と千尋の神隠し」は典型的で、トンネルを通った先の他界の家でグレードマザーと対面し、試練を受ける話です。
部族社会での成人儀礼では、再生時に、その部族の基礎的な宇宙観を教えられます。
多くの場合、知識は神話の伝授として、試練は神話上の英雄の行為の追体験として行われます。
成人が理解し獲得すべき「文化」は、神話では「文化英雄」と呼ばれる存在や、氏族の「始祖」がもたらしたものです。
<成熟儀礼>
多くの神話では「文化(智恵)の獲得」は同時に「死の発生」、「楽園喪失」でもあったと語られます。
合理的な理性や文化の獲得には、永遠性を喪失するという負の面があるわけです。
神話によっては、文化をもたらした英雄が、その後、再度、「不死の獲得」に向けて旅立ちます。
成人後の「成熟の儀礼」の原型をここに見ることができます。
部族によって様々ですが、アボリジニーなどでは、成人の後にも、年齢に沿って何度も「通過儀礼」を行う部族があります。
また、部族内の秘密結社が多数の位階を持ち、位階を昇るごとに「通過儀礼」を行う場合もあります。
「通過儀礼」では、成熟するにつれてより深く潜在意識の智恵を獲得することが求められます。
成熟のプロセスは、心理的に言えば、心の内面に尽きることのない創造力を見出して、人格を成長させることです。
神話的には「若返りの水」「生命の木の実」の獲得などとしても語られます。
シャーマンの「通過儀礼」は、成熟の儀礼のモデルになります。
普通の「成人儀礼」とは異なり、深い自我の解体と霊的知識の獲得が必要とされます。
また、死を前にした人が、死を受け入れ、人生観を新たにし、人格を変容させること(スピリチュアルワーク)は、生前での最後の通過儀礼です。
少年少女を主人公にした童話には「成人儀礼」を元にしたものが多いのですが、老人を主人公にした昔話には成熟を示すものがあります。
昔話では、通常の生活上の判断を否定して利他的な行動をとると、意図せずして富を得るという形になります。
品物を売らずにあげる(笠地蔵)、動物を捕まえずに助けるなどです。
「花咲爺さん」では、犬が何度も意地悪爺さんに殺されながらも、犬→木→臼→灰→桜とメタモルフォーゼを繰り返し、潜在意識や自然の持つ不死なる創造性をこれでもかと示します。
犬が経る死と再生の一回一回が、成熟に向けた通過儀礼のようにも思えます。
ジブリ作品だと、「風の谷のナウシカ」、「もののけ姫」、「ゲド戦記」、「ハウルの動く城」などは「成熟の物語」でしょう。
いずれも、人間の利己的な行為によって、自然=無意識が創造性を失っている状態から物語が始まります。
特に「風の谷のナウシカ」は典型的で、自然=無意識を再生させる偉大なシャーマンになる話です。
<供養>
供養は、主に③のプロセスを歩む死者の「通過儀礼」として行います。
ですが、これを主催し、参加するのは、この世の①②の段階にいる生者です。
供養は、それを行う側の人間にとっても、一種の「通過儀礼」と同様の意味を持ちます。
肉親の供養は、死と対面する機会であり、成長の機会でもあるからです。
また、死者は目指すべき人格モデルでもあり、潜在意識の中の人格でもあり、それとの対話は無意識との対話を通した人格変容でもあります。
「祖霊」や「ホトケ」は古い表現ですが、今風に「心の奥底の声」とか「本当の自分」とで表現することも可能です。
死者との対話の中で、死者の人格は徐々に普遍化していき、それに応じて、生者の人格も普遍化をうながされます。
伝統的な文化では、人間(の魂)を大きなライフサイクル(生命循環)の中で考えます。
この世に誕生し、成長して成人し、成熟して長老になり、亡くなってあの世に行き、個性を脱して祖霊(祖神)になり、子孫を見守り、やがて子孫としてこの世に再生する、というサイクルです。
人(の魂)は、このライフサイクルを歩む中で、いくつもの違った身分(人格・神格)を経ていきます。
その身分を変化させる時々に、「通過儀礼(イニシエーション)」を経ます。
分かりやすい例では、成人式や結婚式、葬式などが「通過儀礼」です。
「通過儀礼」の意味は、古い人格(身分・地位)として死に、新しい人格として再生する「擬死再生」です。
その際に、あるいは、その条件として、必要な知識、能力を身に付けます。
「死」の体験は、様々な演劇的演出によってなされることが多くあります。
幻覚性の薬物を利用する場合もあります。
<4つのプロセス>
ライフサイクルは大きく4つのプロセス(期間)に分けることができます。
① 成長のプロセス :誕生→成人:この世での個別化
② 成熟のプロセス :成人→死 :この世での普遍化
③ 祖神化のプロセス:死→祖神 :あの世での普遍化
④ 祖神としての期間:祖神→誕生:あの世からの個別化
③④は、儀礼を主催するこの世の人間の側から見ると、③が供養、④が先祖祭になります。
ライフサイクルは、「この世(①②)」⇔「あの世(③④)」の循環です。
誕生には「受胎→出産」という中間段階があります。
死にも「葬儀→埋葬」という「中有」とか「もがり」と呼ばれる中間段階があります。
また、ライフサイクルは、「普遍化(②③)」⇔「個別化(④①)」という循環でもあります。
人は誕生後、個性化・個別化して、その極である成人に至ります。
成人した人は、個人を超えて、成熟の道を歩みます。
死は普遍化の道であり、死後の魂もその道を歩み、祖神という普遍化の極に至ります。
そして、祖神の分霊として、再度、個人が再誕します。
各プロセスには、細かくいくつものプロセス(身分と通過儀礼)があります。
少し前の日本の例では…
① 成長のプロセス
誕生(受胎→出産)→名付祝→初宮詣→七五三(子供組加入)→十三参り→成人式(若衆組加入)→結婚・就職
この成人になるには、社会的な知識、合理的な智恵、生活力が必要です。
② 成熟のプロセス
隠居→年祝(還暦→古稀→喜寿→傘寿→米寿…)・年寄(長老)
子供が独立すると隠居になりましたが、これは年齢的にはかなり若い時(40才前くらい)、になります。
他にも、念仏講や庚申講に参加したり、受戒を受けたり、死に備えた段階があります。
成熟には、社会的な調停能力、社会的価値観を相対化する視点、利他精神、無意識の創造力の受容が必要です。
③ 祖神化のプロセス
葬儀(死霊化)→埋葬(精霊化)→年忌法要(祖霊化)→弔い上げ(祖神・氏神化)
祖霊・祖神であれ、浄土に行くホトケであれ、それが普遍的な方向に浄化された魂であることに変わりはありません。
亡くなった人の魂が、悪霊にならずに、この正しい方向に進むようにするのが、葬送と供養の目的です。
水子や幼児の段階で亡くなった場合のように、①②を経ていない魂は、死後に③に進まず、再度、生まれなおすことが望まれます。
④ 祖神の期間
プロセスはありませんが、祖神(祖霊)として子孫を守ります。
祖神(祖霊)は、一般的な氏神の祭り、盆・正月など、定期的にこの世を訪れ、子孫に生命力を与えます。
人はライフサイクルの中で、身分に沿って名前を変えることが一般的でした。
日本人の場合だと、幼名→少年名→家長名→隠居名→戒名・氏神名 といった感じです。
子供には亡くなった祖父母の名を付けることもあります。
独立すると、父から代々の家長としての名を受け継ぎ、父は隠居して祖父から代々の隠居名を受け継ぐ習慣がありました。
<成人儀礼>
成人儀礼の本質は、この世の創造の母体としての他界(=死)と対面して、人格を成長させることでした。
最も原初的な成人儀礼は、洞窟か森の中の儀礼用の小屋で行いました。
洞窟は他界であり、地母神の子宮であり、洞窟から出ることで、新しい人格として再生します。
森も他界であり、小屋は怪物(聖獣)であり、怪物に飲まれ、吐き出されることで再生します。
鯨に飲み込まれたピノキオや、狼に飲み込まれた赤頭巾ちゃんの童話には、原初的な成人式の姿が残っています。
森の中の小屋も、童話の定番です。
他にも、成人儀礼が変形された童話としては、異界に行って、何かを手に入れる(ジャックと豆の木…)とか、何かをやっつける(ヘンデルとグレーテル、一寸法師…)といった形が見られます。
異界に行って戻ることは死と再生の象徴です。
何かを手に入れたり、やっつけたりすることは智恵を獲得する象徴です。
ジブリ作品には成人儀礼の物語が多くあります。
「千と千尋の神隠し」、「となりのトトロ」、「崖の上のポニョ」などは、成女儀礼の物語です。
特に「千と千尋の神隠し」は典型的で、トンネルを通った先の他界の家でグレードマザーと対面し、試練を受ける話です。
部族社会での成人儀礼では、再生時に、その部族の基礎的な宇宙観を教えられます。
多くの場合、知識は神話の伝授として、試練は神話上の英雄の行為の追体験として行われます。
成人が理解し獲得すべき「文化」は、神話では「文化英雄」と呼ばれる存在や、氏族の「始祖」がもたらしたものです。
<成熟儀礼>
多くの神話では「文化(智恵)の獲得」は同時に「死の発生」、「楽園喪失」でもあったと語られます。
合理的な理性や文化の獲得には、永遠性を喪失するという負の面があるわけです。
神話によっては、文化をもたらした英雄が、その後、再度、「不死の獲得」に向けて旅立ちます。
成人後の「成熟の儀礼」の原型をここに見ることができます。
部族によって様々ですが、アボリジニーなどでは、成人の後にも、年齢に沿って何度も「通過儀礼」を行う部族があります。
また、部族内の秘密結社が多数の位階を持ち、位階を昇るごとに「通過儀礼」を行う場合もあります。
「通過儀礼」では、成熟するにつれてより深く潜在意識の智恵を獲得することが求められます。
成熟のプロセスは、心理的に言えば、心の内面に尽きることのない創造力を見出して、人格を成長させることです。
神話的には「若返りの水」「生命の木の実」の獲得などとしても語られます。
シャーマンの「通過儀礼」は、成熟の儀礼のモデルになります。
普通の「成人儀礼」とは異なり、深い自我の解体と霊的知識の獲得が必要とされます。
また、死を前にした人が、死を受け入れ、人生観を新たにし、人格を変容させること(スピリチュアルワーク)は、生前での最後の通過儀礼です。
少年少女を主人公にした童話には「成人儀礼」を元にしたものが多いのですが、老人を主人公にした昔話には成熟を示すものがあります。
昔話では、通常の生活上の判断を否定して利他的な行動をとると、意図せずして富を得るという形になります。
品物を売らずにあげる(笠地蔵)、動物を捕まえずに助けるなどです。
「花咲爺さん」では、犬が何度も意地悪爺さんに殺されながらも、犬→木→臼→灰→桜とメタモルフォーゼを繰り返し、潜在意識や自然の持つ不死なる創造性をこれでもかと示します。
犬が経る死と再生の一回一回が、成熟に向けた通過儀礼のようにも思えます。
ジブリ作品だと、「風の谷のナウシカ」、「もののけ姫」、「ゲド戦記」、「ハウルの動く城」などは「成熟の物語」でしょう。
いずれも、人間の利己的な行為によって、自然=無意識が創造性を失っている状態から物語が始まります。
特に「風の谷のナウシカ」は典型的で、自然=無意識を再生させる偉大なシャーマンになる話です。
<供養>
供養は、主に③のプロセスを歩む死者の「通過儀礼」として行います。
ですが、これを主催し、参加するのは、この世の①②の段階にいる生者です。
供養は、それを行う側の人間にとっても、一種の「通過儀礼」と同様の意味を持ちます。
肉親の供養は、死と対面する機会であり、成長の機会でもあるからです。
また、死者は目指すべき人格モデルでもあり、潜在意識の中の人格でもあり、それとの対話は無意識との対話を通した人格変容でもあります。
「祖霊」や「ホトケ」は古い表現ですが、今風に「心の奥底の声」とか「本当の自分」とで表現することも可能です。
死者との対話の中で、死者の人格は徐々に普遍化していき、それに応じて、生者の人格も普遍化をうながされます。
トーテミズムと先祖信仰 [伝統文化のコスモロジー]
先祖信仰は、その内容に若干の違いはあれども、世界のほとんどの伝統的な文化に見られました。
祖霊の最大の特徴は、個々人の個性を脱した普遍的な霊魂という点です。
<アニミズムとトーテム祖先>
原初的な狩猟文化・部族文化の宗教は、「アニミズム(精霊信仰)」だと言われます。
つまり、人間、動物、植物、さらには、石のような自然物、天体にも、魂が宿っていると考えます。
魂の本質を、非人格的で創造的な「力」であると考える場合は、「マナイズム」などと呼ばれる場合もあります。
何かに宿る、あるいは、何にも宿っていない魂や精霊は、通常は見えません。
ですが、非日常的な時間・意識の状態では、様々な姿で現れて、時には人間のような姿と言葉で語ります。
ですから、原初的な(狩猟)文化では、人間の魂と他の存在の魂(精霊)には本質的な差はないのです。
地上世界での仮の姿が異なるだけです。
現代人は頭ではアニミズムの世界観を信じていませんが、実際は、誰もが無意識的にはアニミズム的な世界を生きています。
様々なものに共感する、擬人的な表現をするという人間的な心情は、アニミズムが基盤になっています。
狩猟文化では、すべての人間、生き物の魂や天体は、地上世界と冥界の間を循環します。
多くの部族では、冥界では人間の魂は、やがて「祖霊(先祖霊)」になります。
「トーテミズム」と呼ばれる信仰を持つ部族社会では、人間の先祖を「トーテム祖先」であると考えます。
「トーテム祖先」は、人間と、動物、あるいは植物、自然物や天体などの魂が融合したような存在です。
ちなみに、現代の進化論も、人間の祖先は、遡るほど人間と他の生物との未分化な存在になります。
トーテムの体系は、一つの部族が共有し、特定の「トーテム祖先」は、部族の中の特定の氏族に固有のものです。
つまり、トーテムは、部族内で氏族を区別する標識です。
例えば、ある氏族のトーテム祖先が「カンガルー」だった場合、その「カンガルー」は、すべての氏族の人間の魂と、カンガルーの魂の元となる根源的魂です。
その分霊が、たまたま地上世界で、仮の姿として、人間として生まれたり、カンガルーとして生まれたりするのです。
トーテムの体系は、結婚制度や食のタブーと強く結びついています。
また、部族によっては、あらゆる存在が、何かのトーテムに分類されます。
つまり、トーテムの体系は、すべての存在を分類する普遍的分類体系、象徴体系なのです。
<祖霊信仰>
新石器時代以降の農耕文化になると、動物とのつながりは薄れ、穀物の生育は人間が管理するようになりました。
おそらく、そのため、人間の魂と他の生き物の魂が、別のものとして区別されるような傾向が生じたのではないでしょうか。
神々や自然の精霊達は必ずしも人間の味方ではありませんが、人間の「祖霊(祖神)」は部族の秩序を守り助けてくれる存在です。
彼らは神の意向を人間に伝えたり、逆に人間の望みを神にとりなしたり、様々な知識を人間に伝授したりします。
また、穀物の豊穣を見守ります。
そして、部族のメンバーを常に監視して、規則を犯した者を罰するとも考えられていました。
<死後と再生>
一般的な先祖信仰では、死後の人間の魂に関して、次のように考えます。
死んだ人間の魂(死霊)は、洞窟や山、川、海などを通って、地下、島、天上などの死者の世界に行きます。
そして、徐々に個性を脱しながら、数十年かかって、集合的な「祖霊(祖神)」に溶け込みます。
アフリカのある部族では、個性を保っている段階の先祖は厳格な性格を持っていて裁く役割を果たし、個性を失った「祖霊」は寛容になって見守ると考えます。
そして、やがて、分霊して、同じ血筋の子孫に生まれ変わります。
ですが、正常ではない魂は、死者の世界に入って「祖霊」になれず、地上を彷徨って死霊のままにとどまり、人間に災いをもたらすと考えられました。
例えば、あまりに悪行を行った人間、恨みを持って死んだ人間、異常な死に方をした人間、若くして死んだ人間、子供を持たずに死んだ人間の魂などです。
また、生まれてまもなく亡くなった場合は、再度、生まれ直すことになります。
また、偉大なシャーマンや英雄的な人間は、個性を残したまま天上などのあの世にとどまり、「祖霊」に溶け込むことも、生まれ変わることもないと考えられました。
死後の人間の魂は徐々に個的な性質を落としていくので、死後の魂、「祖霊(祖神)」には様々なレベルを考えることができます。
・個人的な人格を残した死霊
・氏族としての集合的な祖霊 :氏神、氏族の始祖、トーテム祖先
・部族としての集合的な祖霊 :部族の始祖
・人間全体としての集合的な祖霊:原人間、最初の人間
・生物全体としての集合的な祖霊:至高神の最初の分霊
これはあくまでも理論的に区別できるということであって、各部族がこれらの階層を区別しているということではありません。
「祖霊」は、個的な性質を落とした人間の普遍的で純粋な魂です。
そして、エネルギーに満ちているので、人間とは違った姿をしていて、仮面の姿で現させることも多いようです。
個性を脱した魂というのは、未分化で様々な可能性を秘めている存在ということです。
各氏族のトーテム祖先は特定の特徴を持っていますが、トーテム体系全体を所有する部族の祖先は、そのような個別の特徴は持ちません。
<祖霊と浮遊霊の心理学>
人間の人格は、生まれたばかりの時にはなく、特徴もほとんどありません。
成長し、社会人になるに従って、形成されていきます。
人格は、親/子、男/女、兄弟姉妹、夫/婦、職業…といった様々な性質=ペルソナを鋳型として作られていく側面があります。
その時、潜在意識には、多数のペルソナが作られ、意識はその一方か一部に自己同一化します。
例えば、親と向かい合っている時は子として、子と向かい合っている時は親として、妻と向かいあっている時は夫として、上司と向かい合っている時は部下として、客と向かい合っている時は店員として…などなど、その時々にペルソナを付け替えます。
人間の人格はそのような複数のペルソナの複合体です。
ですが、一人でいる時の人格は、誰かと対している時より、いくぶん透明な、細分化していない特徴の少ない存在になります。
ですが、ユングが主張したように、無意識にはその人の意識にあらわれていない特徴が潜在しています。
無意識全体を考えると、人の魂の特徴は、誰もが多様です。
様々に分化したペルソナ的人格もあれば、未分化な人格的要素もあります。
また、ある人にとっては、付き合いのある他人の人格は、すべて無意識の人格の一つです。
神々や精霊も一種の無意識の人格です。
ですから、通常の人間の意識的な人格は、魂の可能性のごく一部でしかありません。
社会的な制約や意識的な自我の制約をなくすと、通常の人格の多くの部分は、溶けて普遍化していきます。
死後の魂は、そのようにして「祖霊」になっていくと考えられたのでしょう。
死後の魂が普遍化していくと考えることは、宗教や神秘主義、シャーマンなどの修行によって、人格を統合・変容させていくことと似ています。
また、異常な人間の魂が、「祖霊化」せずに浮遊霊となって地上の人間に悪い影響を与えるとする考え方には、心理的には、抑圧や後悔、強いショックなどに関わる、未完了なままに残された心的要素に現れる現象と類似しています。
本来、意識に現れる心的要素は、意識によって何らかの処理、受容が必要なものであって、そういった作業を完了する必要があります。
「祖霊」になっていく死霊は、そのような完了した、あるいは、完了に向かっている心的・人格的要素と似ています。
それに対して、処理されずに抑圧によって無意識に送られた心的要素(コンプレックス)は、時には強迫的に、意識に何度も再帰し続け、心身を脅かしたり、意識の変容を迫ったりします。
強いショックを受けた体験の記憶や、後悔なども、このような心的現象を引き起こします。
こういった未完了な心的要素は、人間に悪影響を与える浮遊霊と似ています。
祖霊の最大の特徴は、個々人の個性を脱した普遍的な霊魂という点です。
<アニミズムとトーテム祖先>
原初的な狩猟文化・部族文化の宗教は、「アニミズム(精霊信仰)」だと言われます。
つまり、人間、動物、植物、さらには、石のような自然物、天体にも、魂が宿っていると考えます。
魂の本質を、非人格的で創造的な「力」であると考える場合は、「マナイズム」などと呼ばれる場合もあります。
何かに宿る、あるいは、何にも宿っていない魂や精霊は、通常は見えません。
ですが、非日常的な時間・意識の状態では、様々な姿で現れて、時には人間のような姿と言葉で語ります。
ですから、原初的な(狩猟)文化では、人間の魂と他の存在の魂(精霊)には本質的な差はないのです。
地上世界での仮の姿が異なるだけです。
現代人は頭ではアニミズムの世界観を信じていませんが、実際は、誰もが無意識的にはアニミズム的な世界を生きています。
様々なものに共感する、擬人的な表現をするという人間的な心情は、アニミズムが基盤になっています。
狩猟文化では、すべての人間、生き物の魂や天体は、地上世界と冥界の間を循環します。
多くの部族では、冥界では人間の魂は、やがて「祖霊(先祖霊)」になります。
「トーテミズム」と呼ばれる信仰を持つ部族社会では、人間の先祖を「トーテム祖先」であると考えます。
「トーテム祖先」は、人間と、動物、あるいは植物、自然物や天体などの魂が融合したような存在です。
ちなみに、現代の進化論も、人間の祖先は、遡るほど人間と他の生物との未分化な存在になります。
トーテムの体系は、一つの部族が共有し、特定の「トーテム祖先」は、部族の中の特定の氏族に固有のものです。
つまり、トーテムは、部族内で氏族を区別する標識です。
例えば、ある氏族のトーテム祖先が「カンガルー」だった場合、その「カンガルー」は、すべての氏族の人間の魂と、カンガルーの魂の元となる根源的魂です。
その分霊が、たまたま地上世界で、仮の姿として、人間として生まれたり、カンガルーとして生まれたりするのです。
トーテムの体系は、結婚制度や食のタブーと強く結びついています。
また、部族によっては、あらゆる存在が、何かのトーテムに分類されます。
つまり、トーテムの体系は、すべての存在を分類する普遍的分類体系、象徴体系なのです。
<祖霊信仰>
新石器時代以降の農耕文化になると、動物とのつながりは薄れ、穀物の生育は人間が管理するようになりました。
おそらく、そのため、人間の魂と他の生き物の魂が、別のものとして区別されるような傾向が生じたのではないでしょうか。
神々や自然の精霊達は必ずしも人間の味方ではありませんが、人間の「祖霊(祖神)」は部族の秩序を守り助けてくれる存在です。
彼らは神の意向を人間に伝えたり、逆に人間の望みを神にとりなしたり、様々な知識を人間に伝授したりします。
また、穀物の豊穣を見守ります。
そして、部族のメンバーを常に監視して、規則を犯した者を罰するとも考えられていました。
<死後と再生>
一般的な先祖信仰では、死後の人間の魂に関して、次のように考えます。
死んだ人間の魂(死霊)は、洞窟や山、川、海などを通って、地下、島、天上などの死者の世界に行きます。
そして、徐々に個性を脱しながら、数十年かかって、集合的な「祖霊(祖神)」に溶け込みます。
アフリカのある部族では、個性を保っている段階の先祖は厳格な性格を持っていて裁く役割を果たし、個性を失った「祖霊」は寛容になって見守ると考えます。
そして、やがて、分霊して、同じ血筋の子孫に生まれ変わります。
ですが、正常ではない魂は、死者の世界に入って「祖霊」になれず、地上を彷徨って死霊のままにとどまり、人間に災いをもたらすと考えられました。
例えば、あまりに悪行を行った人間、恨みを持って死んだ人間、異常な死に方をした人間、若くして死んだ人間、子供を持たずに死んだ人間の魂などです。
また、生まれてまもなく亡くなった場合は、再度、生まれ直すことになります。
また、偉大なシャーマンや英雄的な人間は、個性を残したまま天上などのあの世にとどまり、「祖霊」に溶け込むことも、生まれ変わることもないと考えられました。
死後の人間の魂は徐々に個的な性質を落としていくので、死後の魂、「祖霊(祖神)」には様々なレベルを考えることができます。
・個人的な人格を残した死霊
・氏族としての集合的な祖霊 :氏神、氏族の始祖、トーテム祖先
・部族としての集合的な祖霊 :部族の始祖
・人間全体としての集合的な祖霊:原人間、最初の人間
・生物全体としての集合的な祖霊:至高神の最初の分霊
これはあくまでも理論的に区別できるということであって、各部族がこれらの階層を区別しているということではありません。
「祖霊」は、個的な性質を落とした人間の普遍的で純粋な魂です。
そして、エネルギーに満ちているので、人間とは違った姿をしていて、仮面の姿で現させることも多いようです。
個性を脱した魂というのは、未分化で様々な可能性を秘めている存在ということです。
各氏族のトーテム祖先は特定の特徴を持っていますが、トーテム体系全体を所有する部族の祖先は、そのような個別の特徴は持ちません。
<祖霊と浮遊霊の心理学>
人間の人格は、生まれたばかりの時にはなく、特徴もほとんどありません。
成長し、社会人になるに従って、形成されていきます。
人格は、親/子、男/女、兄弟姉妹、夫/婦、職業…といった様々な性質=ペルソナを鋳型として作られていく側面があります。
その時、潜在意識には、多数のペルソナが作られ、意識はその一方か一部に自己同一化します。
例えば、親と向かい合っている時は子として、子と向かい合っている時は親として、妻と向かいあっている時は夫として、上司と向かい合っている時は部下として、客と向かい合っている時は店員として…などなど、その時々にペルソナを付け替えます。
人間の人格はそのような複数のペルソナの複合体です。
ですが、一人でいる時の人格は、誰かと対している時より、いくぶん透明な、細分化していない特徴の少ない存在になります。
ですが、ユングが主張したように、無意識にはその人の意識にあらわれていない特徴が潜在しています。
無意識全体を考えると、人の魂の特徴は、誰もが多様です。
様々に分化したペルソナ的人格もあれば、未分化な人格的要素もあります。
また、ある人にとっては、付き合いのある他人の人格は、すべて無意識の人格の一つです。
神々や精霊も一種の無意識の人格です。
ですから、通常の人間の意識的な人格は、魂の可能性のごく一部でしかありません。
社会的な制約や意識的な自我の制約をなくすと、通常の人格の多くの部分は、溶けて普遍化していきます。
死後の魂は、そのようにして「祖霊」になっていくと考えられたのでしょう。
死後の魂が普遍化していくと考えることは、宗教や神秘主義、シャーマンなどの修行によって、人格を統合・変容させていくことと似ています。
また、異常な人間の魂が、「祖霊化」せずに浮遊霊となって地上の人間に悪い影響を与えるとする考え方には、心理的には、抑圧や後悔、強いショックなどに関わる、未完了なままに残された心的要素に現れる現象と類似しています。
本来、意識に現れる心的要素は、意識によって何らかの処理、受容が必要なものであって、そういった作業を完了する必要があります。
「祖霊」になっていく死霊は、そのような完了した、あるいは、完了に向かっている心的・人格的要素と似ています。
それに対して、処理されずに抑圧によって無意識に送られた心的要素(コンプレックス)は、時には強迫的に、意識に何度も再帰し続け、心身を脅かしたり、意識の変容を迫ったりします。
強いショックを受けた体験の記憶や、後悔なども、このような心的現象を引き起こします。
こういった未完了な心的要素は、人間に悪影響を与える浮遊霊と似ています。
農耕文化の天地聖婚・穀霊信仰 [伝統文化のコスモロジー]
このページでは、新石器時代以降に生まれた農耕文化の宗教的コスモロジーを、別ページで紹介した狩猟文化のそれと対比してモデル化します。
<天の男神と地の女神の聖婚>
シャーマンに関して対比すれば、狩猟文化が脱魂型の男性シャーマンが中心だったのに対して、農耕文化では憑依型の女性シャーマン(霊媒、巫女)が中心となります。
冥界に行くこと、動物の魂を冥界に送ることは、死に関わるので男性の仕事であり、現世に魂を呼ぶことは、生に関わるので女性の仕事なのです。
そして、狩猟文化の男性シャーマンの相手となる神は、「冥界の女神(原地母神、動物の女主)」であり、農耕文化の女性シャーマンの相手となる神は「天空の男神(太陽神、嵐神)」です。
・狩猟文化:脱魂型男性シャーマン―原地母神(動物の女主)
・農耕文化:憑依型女性シャーマン―天空男神(太陽神・嵐神)
狩猟文化では、「祖霊」が動物の再生や豊猟に関わることはあまりありませんでした。
ですが、農耕は、人工的に作られた田畑を人間が管理します。
おおらくそのためか、農耕文化では「祖霊」が穀物の生育を見守ります。
ですが、必要な自然の力もあって、主なものは、太陽の光・熱と、水です。
そのため、最も重要な豊穣神は、太陽神や嵐神(雷神、雨神)のような天空神です。
どんな神が重視されるかは地域によって特性があります。
雷神、雨神は、狩猟文化では月神の働きのような存在でしたが、農耕文化では月神より太陽神の重要性が上がったためか、雷神、雨神と月神との関係は薄れたようです。
そして、穀物の豊穣のためには、これら「天の豊穣神」と、「地の豊穣神(地母神、田畑の女神)が結びつくこと、つまり、「天地の聖婚」が必要となります。
そのため、太陽光や雨、稲妻が、精液や男根に譬えられるようになりました。
また、狩猟文化では地母神と傷つける行為としてタブー視される大地の耕作にも、「聖婚」の観念が生まれ、鍬が男根に譬えることになりました。
狩猟文化の「原地母神」が、息子(=男根)を自身の一部として含む両性具有的存在だったのとは違って、農耕文化の「地母神」は単性の女(母)性神です。
そして、「天神」も単性の男(父)性神であり、男神は「父性原理」として「原地母神」から独立したのです。
また、女性シャーマンは、天空男神の神霊を憑依させると共に、それと聖婚し、その御子神を生んで、出産(ミアレ)します。
一方、農業文化を基にした王国では、王が天空男神の子、あるいは、子孫、化身と見なされて、神として、死と再生や聖婚の儀礼を演じました。
「天地の聖婚」の観念は、天空と地上・地下の分離を意味します。
狩猟文化では、重要性の乏しかった天上、天神が、農耕文化では重要な存在となり、その分、地下の冥界の重要性が減りました。
<季節循環の神話・儀礼>
穀物の育成の管理が必要な農耕文化では、狩猟文化よりも、季節循環の儀礼や神話が重要となりました。
季節循環は、「天の豊饒神」が「不毛神(冬や乾季の神)」や「冥界神」と戦って死んで冥界に落ちたり(バアル、マルドゥク、ホルス神話など)、「穀物神」やその「息子・娘」が「冥界神」によって連れ去られて(デルメル・ペルセポネー神話など)、これらを復活させたり連れ戻すといった形で表現されました。
季節循環は、次のような神話として表現されました。
「天の豊饒神」が「不毛神(冬や乾季の神)」や「冥界神」と戦って死んで冥界に落ちて、豊穣女神に助けられるなどして復活する。(バアル、マルドゥク、ホルス神話など)
「穀物神」やその「息子・娘」が「冥界神」によって連れ去られて、豊穣女神に助けられるなどして地上に戻る。(デルメル・ペルセポネー神話など)
また、豊穣女神は、荒ぶる存在となって不毛神と戦うこともありました。
ですが場合によっては、狂気に落ちて天神や穀物神を殺す存在にもなりました。
ここには、狩猟文化以来の「原地母神」=「冥界母神」として側面が変形されて現れているのでしょう。
天と地下の分離と平行して、善と悪の分離も進みました。
冥界は、豊饒や再生よりも、死や病気をもたらす存在として、悪という性質が強くなりました。
つまり、生命の循環の意味が少し変わって、冥界に行くことは、狩猟文化のような「帰還」や「再生」ではなく、悪に屈するという意味を持つようになりました。
<山の神と聖樹>
麦の畑作や水稲農業の文化の前に、山間部などでの焼畑農業や、イモなど根菜類の栽培農業の文化がありました。
焼畑、根菜農業では、豊穣女神の遺体からの穀物の誕生(ハイヌヴェレ、オオゲツヒメ型神話)や、地母神の火による死(イナザミ)と再生という神話が生まれました。
狩猟文化では、豊穣神である「原地母神」は、「山の神」でもありました。
焼畑農業では、山間の聖地と農地の間を豊穣女神が循環・来去するという観念が生まれました。
また、伐採された焼畑の農地には大きな樹が残され、そこに女神が宿るとされました。
この豊穣女神の循環の観念は、その後、里にある畑や水田にも持ち込まれ、「山の神」が「畑の神」、「田の神」として循環・来去すると考えられるようになりました。
そして、山から切り出された樹が、家、田畑に祀られました(若木迎え、門松、メイポール、クリスマスツリー)。
ですが、田には水が山から流れてきますが、畑は天水なので、「畑の豊穣男神」が天から直接、昇降すると考える場合もあります。
また、日本では、「天の豊穣神」の中でも、雷神は、山に降りて「山の豊穣男神」になることがあります。
狩猟文化では、雷神は月神の蛇体の化身であって、女性と交わる男性神でしたので、農業文化でもこれが継承されています。
ですが、男女の「山の神」が習合することで、性別が不明確になります。
年周期で来去する豊穣神は、春には若い神として来て、秋には老いた神として去ると考えられました。
上に書いたように、巫女が豊穣男神と聖婚して御子神(若宮)を生むと考える場合もあります。
日本では、「山の女神」は、新年に里に降りて、まず、「家の神(竈神)」になり、田に導かれて「田畑の神」になりました。
<穀霊のライフサイクル>
狩猟文化での「動物の魂」に対応するのは、農耕文化においては穀物の魂である「穀霊」です。
穀物は一般の植物とは異なった特別の存在で、食物の女神の遺体から生まれたり、その種が英雄(シャーマン)や鳥によって天上からもたらされたりしたものと考えられました。
狩猟文化では、動物が地上と冥界の「原地母神」の元を循環・来去したように、農耕文化では、「穀霊」が年周期で循環します。
この「穀霊」の再生と共に、宇宙も年周期で更新されるのです。
穀物のライフサイクルは、人間のライフサイクルと同様のものとして、対応して考えられました。
つまり、米や麦が育って穂が実ることは穀母になって受胎・妊娠すること、脱穀することは出産すること、苅取りは死ぬことです。
そして、種を倉庫に保管したり大地に巻いたりすることは、穀童が冥界に落ちること、発芽することは再生することです。
<農耕儀礼>
「天地の聖婚」や「穀霊」のライフサイクルなどの観念に従って、様々な農耕儀礼が行われます。
狩猟文化の流れを引く男性シャーマンがいる場合は、天上や冥界にトリップして種を盗み出したり、悪霊に盗まれた種を取り返したりする儀礼が行われることもあります。
男性秘密結社のメンバーが、村を訪れる「祖霊」に扮して、「穀霊」や「穀物の種」をもたらす場合もあります。
先に書いたように、「祖霊」は、穀物の生育も見守ります。
新年には、実際の農作業に先立って、農作業を模した「予祝儀礼」が行われます。
狩猟文化の影響からか、「儀礼的狩猟」が行われる場合もあります。
水稲農業の田植えは、おそらく、人間で言えば成人に相当する段階です。
日本では、田植えは、早乙女と呼ばれる女性が担当しますが、雷神を誘惑して稲妻と雨を田に導きます。
これは、雷神と田の女神(稲の穀母)との聖婚です。
収穫時には、「初穂儀礼」と「刈り入れ儀礼」が行われます。
東南アジアや沖縄では、脱穀前の初穂と農婦が添い寝をして、出産を模した儀礼を行いました。
そして、初穂を豊穣神に捧げて(穂掛儀礼)、穀物を神と「共食(新嘗祭)」することが重要な儀式になりました。
ヨーロッパでは、乱痴気騒ぎ的な儀礼や、農夫婦が畑で聖婚を演じる儀礼、麦の花嫁と花婿を結婚させる儀礼などが行われます。
また、収穫の後の麦(「婆さん」などと呼ばれます、麦穂から人形を作る場合もあります)を焼いて、その灰を田畑にまくという、死と再生の豊饒儀礼を行います。
<穀霊の秘儀>
農耕文化では、「穀霊」を、人間の魂の原型であり、特に新しく実った復活した「穀霊」が、純粋で生命力溢れる純粋な魂であるとして、信仰の重要な対象になりました。
具体的には、特に、最初に収穫された初穂、地域によっては最後に収穫された穂が神聖視されました。
そして、その穂が「家の守り神」として祀られました。
穂から脱穀された「籾」は出産された嬰児であり、精米された「白米」は「穀霊」と見なされたのでしょう。
狩猟文化の宗教の本質は、原地母神の創造性と一体化することですが、農耕文化の宗教の本質は、再生した穀霊としての純粋な霊魂と一体化することなのです。
<天の男神と地の女神の聖婚>
シャーマンに関して対比すれば、狩猟文化が脱魂型の男性シャーマンが中心だったのに対して、農耕文化では憑依型の女性シャーマン(霊媒、巫女)が中心となります。
冥界に行くこと、動物の魂を冥界に送ることは、死に関わるので男性の仕事であり、現世に魂を呼ぶことは、生に関わるので女性の仕事なのです。
そして、狩猟文化の男性シャーマンの相手となる神は、「冥界の女神(原地母神、動物の女主)」であり、農耕文化の女性シャーマンの相手となる神は「天空の男神(太陽神、嵐神)」です。
・狩猟文化:脱魂型男性シャーマン―原地母神(動物の女主)
・農耕文化:憑依型女性シャーマン―天空男神(太陽神・嵐神)
狩猟文化では、「祖霊」が動物の再生や豊猟に関わることはあまりありませんでした。
ですが、農耕は、人工的に作られた田畑を人間が管理します。
おおらくそのためか、農耕文化では「祖霊」が穀物の生育を見守ります。
ですが、必要な自然の力もあって、主なものは、太陽の光・熱と、水です。
そのため、最も重要な豊穣神は、太陽神や嵐神(雷神、雨神)のような天空神です。
どんな神が重視されるかは地域によって特性があります。
雷神、雨神は、狩猟文化では月神の働きのような存在でしたが、農耕文化では月神より太陽神の重要性が上がったためか、雷神、雨神と月神との関係は薄れたようです。
そして、穀物の豊穣のためには、これら「天の豊穣神」と、「地の豊穣神(地母神、田畑の女神)が結びつくこと、つまり、「天地の聖婚」が必要となります。
そのため、太陽光や雨、稲妻が、精液や男根に譬えられるようになりました。
また、狩猟文化では地母神と傷つける行為としてタブー視される大地の耕作にも、「聖婚」の観念が生まれ、鍬が男根に譬えることになりました。
狩猟文化の「原地母神」が、息子(=男根)を自身の一部として含む両性具有的存在だったのとは違って、農耕文化の「地母神」は単性の女(母)性神です。
そして、「天神」も単性の男(父)性神であり、男神は「父性原理」として「原地母神」から独立したのです。
また、女性シャーマンは、天空男神の神霊を憑依させると共に、それと聖婚し、その御子神を生んで、出産(ミアレ)します。
一方、農業文化を基にした王国では、王が天空男神の子、あるいは、子孫、化身と見なされて、神として、死と再生や聖婚の儀礼を演じました。
「天地の聖婚」の観念は、天空と地上・地下の分離を意味します。
狩猟文化では、重要性の乏しかった天上、天神が、農耕文化では重要な存在となり、その分、地下の冥界の重要性が減りました。
<季節循環の神話・儀礼>
穀物の育成の管理が必要な農耕文化では、狩猟文化よりも、季節循環の儀礼や神話が重要となりました。
季節循環は、「天の豊饒神」が「不毛神(冬や乾季の神)」や「冥界神」と戦って死んで冥界に落ちたり(バアル、マルドゥク、ホルス神話など)、「穀物神」やその「息子・娘」が「冥界神」によって連れ去られて(デルメル・ペルセポネー神話など)、これらを復活させたり連れ戻すといった形で表現されました。
季節循環は、次のような神話として表現されました。
「天の豊饒神」が「不毛神(冬や乾季の神)」や「冥界神」と戦って死んで冥界に落ちて、豊穣女神に助けられるなどして復活する。(バアル、マルドゥク、ホルス神話など)
「穀物神」やその「息子・娘」が「冥界神」によって連れ去られて、豊穣女神に助けられるなどして地上に戻る。(デルメル・ペルセポネー神話など)
また、豊穣女神は、荒ぶる存在となって不毛神と戦うこともありました。
ですが場合によっては、狂気に落ちて天神や穀物神を殺す存在にもなりました。
ここには、狩猟文化以来の「原地母神」=「冥界母神」として側面が変形されて現れているのでしょう。
天と地下の分離と平行して、善と悪の分離も進みました。
冥界は、豊饒や再生よりも、死や病気をもたらす存在として、悪という性質が強くなりました。
つまり、生命の循環の意味が少し変わって、冥界に行くことは、狩猟文化のような「帰還」や「再生」ではなく、悪に屈するという意味を持つようになりました。
<山の神と聖樹>
麦の畑作や水稲農業の文化の前に、山間部などでの焼畑農業や、イモなど根菜類の栽培農業の文化がありました。
焼畑、根菜農業では、豊穣女神の遺体からの穀物の誕生(ハイヌヴェレ、オオゲツヒメ型神話)や、地母神の火による死(イナザミ)と再生という神話が生まれました。
狩猟文化では、豊穣神である「原地母神」は、「山の神」でもありました。
焼畑農業では、山間の聖地と農地の間を豊穣女神が循環・来去するという観念が生まれました。
また、伐採された焼畑の農地には大きな樹が残され、そこに女神が宿るとされました。
この豊穣女神の循環の観念は、その後、里にある畑や水田にも持ち込まれ、「山の神」が「畑の神」、「田の神」として循環・来去すると考えられるようになりました。
そして、山から切り出された樹が、家、田畑に祀られました(若木迎え、門松、メイポール、クリスマスツリー)。
ですが、田には水が山から流れてきますが、畑は天水なので、「畑の豊穣男神」が天から直接、昇降すると考える場合もあります。
また、日本では、「天の豊穣神」の中でも、雷神は、山に降りて「山の豊穣男神」になることがあります。
狩猟文化では、雷神は月神の蛇体の化身であって、女性と交わる男性神でしたので、農業文化でもこれが継承されています。
ですが、男女の「山の神」が習合することで、性別が不明確になります。
年周期で来去する豊穣神は、春には若い神として来て、秋には老いた神として去ると考えられました。
上に書いたように、巫女が豊穣男神と聖婚して御子神(若宮)を生むと考える場合もあります。
日本では、「山の女神」は、新年に里に降りて、まず、「家の神(竈神)」になり、田に導かれて「田畑の神」になりました。
<穀霊のライフサイクル>
狩猟文化での「動物の魂」に対応するのは、農耕文化においては穀物の魂である「穀霊」です。
穀物は一般の植物とは異なった特別の存在で、食物の女神の遺体から生まれたり、その種が英雄(シャーマン)や鳥によって天上からもたらされたりしたものと考えられました。
狩猟文化では、動物が地上と冥界の「原地母神」の元を循環・来去したように、農耕文化では、「穀霊」が年周期で循環します。
この「穀霊」の再生と共に、宇宙も年周期で更新されるのです。
穀物のライフサイクルは、人間のライフサイクルと同様のものとして、対応して考えられました。
つまり、米や麦が育って穂が実ることは穀母になって受胎・妊娠すること、脱穀することは出産すること、苅取りは死ぬことです。
そして、種を倉庫に保管したり大地に巻いたりすることは、穀童が冥界に落ちること、発芽することは再生することです。
<農耕儀礼>
「天地の聖婚」や「穀霊」のライフサイクルなどの観念に従って、様々な農耕儀礼が行われます。
狩猟文化の流れを引く男性シャーマンがいる場合は、天上や冥界にトリップして種を盗み出したり、悪霊に盗まれた種を取り返したりする儀礼が行われることもあります。
男性秘密結社のメンバーが、村を訪れる「祖霊」に扮して、「穀霊」や「穀物の種」をもたらす場合もあります。
先に書いたように、「祖霊」は、穀物の生育も見守ります。
新年には、実際の農作業に先立って、農作業を模した「予祝儀礼」が行われます。
狩猟文化の影響からか、「儀礼的狩猟」が行われる場合もあります。
水稲農業の田植えは、おそらく、人間で言えば成人に相当する段階です。
日本では、田植えは、早乙女と呼ばれる女性が担当しますが、雷神を誘惑して稲妻と雨を田に導きます。
これは、雷神と田の女神(稲の穀母)との聖婚です。
収穫時には、「初穂儀礼」と「刈り入れ儀礼」が行われます。
東南アジアや沖縄では、脱穀前の初穂と農婦が添い寝をして、出産を模した儀礼を行いました。
そして、初穂を豊穣神に捧げて(穂掛儀礼)、穀物を神と「共食(新嘗祭)」することが重要な儀式になりました。
ヨーロッパでは、乱痴気騒ぎ的な儀礼や、農夫婦が畑で聖婚を演じる儀礼、麦の花嫁と花婿を結婚させる儀礼などが行われます。
また、収穫の後の麦(「婆さん」などと呼ばれます、麦穂から人形を作る場合もあります)を焼いて、その灰を田畑にまくという、死と再生の豊饒儀礼を行います。
<穀霊の秘儀>
農耕文化では、「穀霊」を、人間の魂の原型であり、特に新しく実った復活した「穀霊」が、純粋で生命力溢れる純粋な魂であるとして、信仰の重要な対象になりました。
具体的には、特に、最初に収穫された初穂、地域によっては最後に収穫された穂が神聖視されました。
そして、その穂が「家の守り神」として祀られました。
穂から脱穀された「籾」は出産された嬰児であり、精米された「白米」は「穀霊」と見なされたのでしょう。
狩猟文化の宗教の本質は、原地母神の創造性と一体化することですが、農耕文化の宗教の本質は、再生した穀霊としての純粋な霊魂と一体化することなのです。
縄文文化と月信仰 [伝統文化のコスモロジー]
規則的に満ち欠けを繰り返す月は、「再生」、「不死」、「豊穣」、そして、「時」と「秩序」の象徴であり、それを司る神です。
また、女性の月経を支配する、つまり、人間の出産を司る存在です。
そして、潮の干満を支配する、つまり、水の流れを司る存在です。
縄文文化は原地母神という女性原理の能産力、再生力を信仰の中心としていたので、必然的に月信仰を重視していました。
その後の倭国も、海の民(魚撈民)の影響の強い国でした。
海の民は、生活にとって何よりも重要な「潮」を支配する月を信仰していたと考えるのが妥当です。
実際、古代の日本は太陰暦を使用していましたし、多くの祭は満月の夜に行われました。
これは月を信仰していたからでしょう。
<再生を願う月信仰>
月は、自身が再生する存在であり、また、再生力、生命力を与えることで自然や人間の再生を可能とする存在です。
月は、一ヶ月周期で満ち、欠けます。
そして、3日間の死を経て新月(朔から三日月)として再生します。
月の明るい部分は、生命力、再生力が満ちていて、それによって光っています。
月の生命力、再生力は、月光として、稲妻として、あるいは、「変若水(おちみず、若返りの水、生命の水)」として、または、それを飲んだ蛇を通して、自然、人間に与えられます。
「変若水」は、主に雨を通して、あるいは、露という形で地上に下り、自然に吸収されます。
月は、「原地母神(太母)」の一部であるか、一体の存在、あるいは、密接に関係のある存在です。
月を象徴する図形には、「三角形」、「菱形」、「波線(蛇行線)」、「螺旋」などがあります。
月は、3日間、死んでから再生すると考えられたので、数字の「3」は、月(新月、三日月)を象徴します。
月の動物は、三本指であったり、三本足だったりします。
復活した三日月(新月)の象徴には、牛などの「角」、イノシシの「牙」があります。
「勾玉」もそうです。
<土偶>
縄文の土遇には、再生力の象徴である月信仰が表現されています。
涙、鼻水、ヨダレを流している土偶がありますが、これは月神が「変若水」を下していることを表現しています。
縄文の土偶の多くの口が開いているのは、「変若水」を受ける取るためです。
顔が平たく、上を向いているのも、頭上に取入口がある中空構造になっているのも、「変若水」を受けて入れるためです。
土偶が腕(脇)を広げているのは、新月の後に月光を切望している姿です。
三角の顔、ハート型(三日月を2つ合わせた形)の顔は、月神を表現します。
細長い目や眉毛は、三日月を表現しています。
遮光土偶は、赤ん坊の寝顔を表現していて、これは誕生した新月を表現しています。
<月の動物:蛇、蛙、兎、馬、蚕>
「蛇」は、何よりも脱皮して再生する点が、そして、鱗が光る、蛇行するなどの点が、月と共通しているので、月を象徴する動物です。
そして、「蛇」は、月の「変若水」を飲んだ存在であり、それを運ぶ存在です。
月神は、蛇となって人間の女性と交わります。
中でも海の彼方からやってくるセグロウミヘビが月神の化身でした。
「雷(稲妻)」は、光る(熱なく光る)点が、そして、蛇行し、雨(変若水)を導く点が、月神と似ているので、月の働きであり、「蛇」でもあります。
月神の性別ははっきりしませんが、女性と交わる蛇や稲妻は、男性です。
「蛙(ヒキガエル)」は、雨を呼ぶ点で、そして、冬眠から復活し、その背が月の模様に似ているなどの点で、月と関係する動物とされます。
「ヒキガエル」は、月に飛びついて、その模様になったという神話が、各地のモンドロイドにあります。
また、月の「暗」の部分の象徴でもあり、また、大地の象徴でもあります。
古代中国の三星堆文明では、月の模様から、月で「兎」が「不死の霊薬」をついていると考えられました。
「兎」は、月の「明」の部分の象徴でもありました。
おそらく、古い時代に、日本にもこれが伝わったのでしょう。
日本でも、「兎」は月と関係の深い動物とされます。
「馬」は月の飛行力を象徴する動物であり、月神への犠牲獣でした。
「古事記」に出てくる「天の斑駒」は月のような模様を持った馬であり、月神の化身でしょう。
「蚕」は月の虫、常世の虫です。
「蚕」の背には、「馬」の蹄の模様があります。
「蚕」は、最初は黒い姿(新月)ですが、何度か脱皮(再生)しながら1ヶ月ほどで満月のような繭に籠もって白い姿で復活します。
つまり、満ちていく月なのです。
そして、繭から作られた糸、それを織った衣は、月の光を放ちます。
ちなみに、日の巫女とされる「ヒルメ」の「ヒル」は、糸を延べて戻す作業のことで、「ヒルメ」とは月の巫女である「機織女」のことです。
中国の「捜神記」中の「女化蚕」や、日本の「遠野物語」のオシラ様の説話などで知られる養蚕神話(馬娘婚姻譚)は、剥がれた馬の皮が娘を包んで蚕(神)となったという神話です。
「蚕」と「馬」が結び付けられていますが、それを背景で結びつけているのは月信仰でしょう。
ちなみに、古代中国の三星堆文明(揚子江文明)の西大母の神話には、月、蚕、兎、ヒキガエルが揃っていました。
<月と動物と機織女>
機織女と蚕とヒキガエル、馬を登場させて、古代日本の月信仰を再構成してみましょう。
雨(=変若水)が降らず、自然の生命力が衰退した時、ヒキガエルが月に雨を祈願して鳴きます。
月は「変若水」を地上に落とすことで、自然を復活させます。
ですが、月は自身の生命力を失って欠けていき、深夜に空高くで輝くこともできなくなります。
そして、とうとう岩屋の中に隠れてしまい、夜の世界は暗闇となります。
月の再生を祈って、月に仕える巫女(機織女)も忌み籠りします。
月の生命力は自然が吸収します。
月の虫である蚕は桑を食べて、その中にある生命力を集めます。
蚕は黒い姿(新月)から白い姿(満月)へと、何度も脱皮しながら1ケ月かかって成長し、繭(満月)を作って変態します。
機織女は、月の生命力が凝縮した繭から絹を紡ぎ、光る衣(領巾・神衣・天の羽衣)を織り上げます。
規則正しく機を織る作業は、時と秩序と豊穣の月の特徴と重なります。
機織女は完成した領巾を振る呪術によって、月に生命力、光を返します。
また、馬を供犠として捧げます。
こうして、月は復活し、満ちゆき、馬の飛行力によって天高くで輝くことができるようになります。
<万葉集、出雲国風土記と月信仰>
「万葉集」に表現された世界観は、記紀神話に比較すると、政治的に改変された側面が少ないと思われます。
「万葉集」には月の歌は多く、太陽の歌は数少ないのです。
つまり、古代日本では、月信仰の方が強かったのです。
そして、「アマテル」という言葉は、月を形容する常套形容句(海を照らす月)でした。
つまり、「アマテル(アマラス)」は、本来は月の女神、あるいは、月の巫女神であり機織女を指す名前だったのでしょう。
実際、伊勢神宮の内宮の神楽歌にも、「アマテラス」を月とする歌が残っています。
また、内宮の秘伝書「倭姫命世紀」には、荒祭宮の多賀宮に祀られているアマテラスの和魂が「月天子」であると書かれています。
また、アマテラスの荒魂とされる「アマサカルムカツヒメ」の「天さかる向か」とは、月が西の天の極みに向かって昇ることを意味する常套句です。
さらには、本来の皇祖神であるタカミムスヒ(高木神)も槻に付く月神です。
「ムス」は再生を意味します。
そして、オオヒルメノムチ(=天照大神)はそれに仕える巫女です。
ちなみに、天皇を表す「スメラ」は月を表す「澄む」から来た言葉です。
また、天皇に名に現れる「タラシヒコ」の「足る」は月が満ちることを意味します。
*この項ここまで、三浦茂久「古代日本の月信仰と再生思想」を参照
三日月を表現する勾玉を神宝として重視する古代出雲には、月信仰が濃厚にあったはずです。
「出雲国風土記」に語られる加賀伝承は、月母神の創世神話だったはずですが、大和朝廷の意図によって改変されています。
本来の加賀伝承では、佐太大神の母、輝く支佐加比売(キサカヒヒメ)は月女神です。
洞窟の主であり、満月でもあったこの女神が、金の弓によって太陽を射落として新月の御子(=勾玉)である佐太大神(=オオナムチ)を生みました。
「加賀(カガ)」は、月光の輝きを意味します。
「佐太(サタ)」は、「更」+「足」、つまり、再生した満ちる月を意味します。
「猿田彦」も「佐太大神」と同じ神でしょう。
また、「出雲国風土記」に登場する神のアジスタカヒコは、大きな声で泣く児童神で、梯子を昇降します。
この神は、「変若水」垂らす新月、あるいは、「変若水」や稲妻として月から下り、また月に戻る神でしょう。
この神は、記紀神話のスサノオのモデルの一人だったのかもしれません。
*この項ここまで、ネリー・ナウマン「光の神話考古」掲載の坂田千鶴子「『出雲国風土記』砕かれた縄文槻神話の復元」を参照
<記紀神話と月信仰>
記紀神話は、縄文以来の月信仰を隠しました。
ですが、わずかに、その断片や改変された姿が残っています。
「日本書紀」では、月神のツクヨミがウケモチを殺すと、その死体の各所から穀物や蚕、牛馬が生まれます。 数少ない月に関する神話です。
この神話の背景には、月神が自然の死と再生を司る豊穣神と考えられていたことがあります。
「古事記」では、アマテラスが機屋で神に奉げる衣を織らせていた時、スサノオは機屋の屋根に穴を開けて、そこから皮を逆剥ぎにした天の斑馬を落とし入れます。
そのため、織織女が驚いて梭(ひ)で陰部を刺して死んでしまい、それに怒ったアマテラスは天岩屋に引き篭ります。
上に書いたように、馬は月の飛行力を象徴する動物であり、月神のツクヨミは馬に乗ります。
そのためか、馬は月神への犠牲獣でした。
スサノヲが馬を投げ入れたのは、馬を供犠にしたことが背景にあるのでしょう。
斑馬は月のような模様を持った馬であり、皮を剥がれているのは、光(=皮)を失った新月のことかもしれません。
であれば、岩戸に篭もったのは、アマテラス月女神です。
アマテラスは月の巫女であって、機屋に籠って、月を復活させる衣(=光)を織っていたのかもしれません。
また、アマテラスを岩屋から引き出す時に使った「鏡」は本来、満月の象徴でした。
「古事記」の出雲神話である「因幡の白兎」にも、その古層に月の神話があったと思われます。
因幡の白兎は海峡を渡るため、ワニを騙して一列に並ばせたワニの上を数えながら渡っていきますが、最後に嘘がばれて皮を剥がれます。
白兎が泣いていると、オオナムチが来て、治療法を教えてくれて治ります。
兎は月の明部の象徴ですから、ワニは暗部の象徴でしょう。
ワニを数えて海を渡るのは、月を読むこと(ツクヨミ)、つまり日を数えることです。
白兎が皮を剥がれるのは、満月が徐々に欠けて新月になるからです。
白兎が泣くのは、月が「変若水」を自然に降らすためです。
オオナムチには、復活した新月の神という性質が隠れています。
<月神話の心理学的意味>
太陽が意識的自我の象徴なら、月は無意識的な自己の象徴です。
古代の世界観においては、後者を重視し、後者が前者の創造力の基盤でした。
特に、狩猟文化では、女性原理の生む力を信仰し、人工的に田畑を管理する農耕文化とは違って、自然の森の中へ動物を迎えに行くので、後者を重視します。
太陽の死と再生を考えることは、意識の創造力を考えることです。
ですが、月の死と再生を考えることは、無意識の創造力を考えることです。
後者は、前者の基盤です。
月の死と再生を心に刻むことは、より深い創造力と、人格の成熟を導くことができます。
また、女性の月経を支配する、つまり、人間の出産を司る存在です。
そして、潮の干満を支配する、つまり、水の流れを司る存在です。
縄文文化は原地母神という女性原理の能産力、再生力を信仰の中心としていたので、必然的に月信仰を重視していました。
その後の倭国も、海の民(魚撈民)の影響の強い国でした。
海の民は、生活にとって何よりも重要な「潮」を支配する月を信仰していたと考えるのが妥当です。
実際、古代の日本は太陰暦を使用していましたし、多くの祭は満月の夜に行われました。
これは月を信仰していたからでしょう。
<再生を願う月信仰>
月は、自身が再生する存在であり、また、再生力、生命力を与えることで自然や人間の再生を可能とする存在です。
月は、一ヶ月周期で満ち、欠けます。
そして、3日間の死を経て新月(朔から三日月)として再生します。
月の明るい部分は、生命力、再生力が満ちていて、それによって光っています。
月の生命力、再生力は、月光として、稲妻として、あるいは、「変若水(おちみず、若返りの水、生命の水)」として、または、それを飲んだ蛇を通して、自然、人間に与えられます。
「変若水」は、主に雨を通して、あるいは、露という形で地上に下り、自然に吸収されます。
月は、「原地母神(太母)」の一部であるか、一体の存在、あるいは、密接に関係のある存在です。
月を象徴する図形には、「三角形」、「菱形」、「波線(蛇行線)」、「螺旋」などがあります。
月は、3日間、死んでから再生すると考えられたので、数字の「3」は、月(新月、三日月)を象徴します。
月の動物は、三本指であったり、三本足だったりします。
復活した三日月(新月)の象徴には、牛などの「角」、イノシシの「牙」があります。
「勾玉」もそうです。
<土偶>
縄文の土遇には、再生力の象徴である月信仰が表現されています。
涙、鼻水、ヨダレを流している土偶がありますが、これは月神が「変若水」を下していることを表現しています。
縄文の土偶の多くの口が開いているのは、「変若水」を受ける取るためです。
顔が平たく、上を向いているのも、頭上に取入口がある中空構造になっているのも、「変若水」を受けて入れるためです。
土偶が腕(脇)を広げているのは、新月の後に月光を切望している姿です。
三角の顔、ハート型(三日月を2つ合わせた形)の顔は、月神を表現します。
細長い目や眉毛は、三日月を表現しています。
遮光土偶は、赤ん坊の寝顔を表現していて、これは誕生した新月を表現しています。
<月の動物:蛇、蛙、兎、馬、蚕>
「蛇」は、何よりも脱皮して再生する点が、そして、鱗が光る、蛇行するなどの点が、月と共通しているので、月を象徴する動物です。
そして、「蛇」は、月の「変若水」を飲んだ存在であり、それを運ぶ存在です。
月神は、蛇となって人間の女性と交わります。
中でも海の彼方からやってくるセグロウミヘビが月神の化身でした。
「雷(稲妻)」は、光る(熱なく光る)点が、そして、蛇行し、雨(変若水)を導く点が、月神と似ているので、月の働きであり、「蛇」でもあります。
月神の性別ははっきりしませんが、女性と交わる蛇や稲妻は、男性です。
「蛙(ヒキガエル)」は、雨を呼ぶ点で、そして、冬眠から復活し、その背が月の模様に似ているなどの点で、月と関係する動物とされます。
「ヒキガエル」は、月に飛びついて、その模様になったという神話が、各地のモンドロイドにあります。
また、月の「暗」の部分の象徴でもあり、また、大地の象徴でもあります。
古代中国の三星堆文明では、月の模様から、月で「兎」が「不死の霊薬」をついていると考えられました。
「兎」は、月の「明」の部分の象徴でもありました。
おそらく、古い時代に、日本にもこれが伝わったのでしょう。
日本でも、「兎」は月と関係の深い動物とされます。
「馬」は月の飛行力を象徴する動物であり、月神への犠牲獣でした。
「古事記」に出てくる「天の斑駒」は月のような模様を持った馬であり、月神の化身でしょう。
「蚕」は月の虫、常世の虫です。
「蚕」の背には、「馬」の蹄の模様があります。
「蚕」は、最初は黒い姿(新月)ですが、何度か脱皮(再生)しながら1ヶ月ほどで満月のような繭に籠もって白い姿で復活します。
つまり、満ちていく月なのです。
そして、繭から作られた糸、それを織った衣は、月の光を放ちます。
ちなみに、日の巫女とされる「ヒルメ」の「ヒル」は、糸を延べて戻す作業のことで、「ヒルメ」とは月の巫女である「機織女」のことです。
中国の「捜神記」中の「女化蚕」や、日本の「遠野物語」のオシラ様の説話などで知られる養蚕神話(馬娘婚姻譚)は、剥がれた馬の皮が娘を包んで蚕(神)となったという神話です。
「蚕」と「馬」が結び付けられていますが、それを背景で結びつけているのは月信仰でしょう。
ちなみに、古代中国の三星堆文明(揚子江文明)の西大母の神話には、月、蚕、兎、ヒキガエルが揃っていました。
<月と動物と機織女>
機織女と蚕とヒキガエル、馬を登場させて、古代日本の月信仰を再構成してみましょう。
雨(=変若水)が降らず、自然の生命力が衰退した時、ヒキガエルが月に雨を祈願して鳴きます。
月は「変若水」を地上に落とすことで、自然を復活させます。
ですが、月は自身の生命力を失って欠けていき、深夜に空高くで輝くこともできなくなります。
そして、とうとう岩屋の中に隠れてしまい、夜の世界は暗闇となります。
月の再生を祈って、月に仕える巫女(機織女)も忌み籠りします。
月の生命力は自然が吸収します。
月の虫である蚕は桑を食べて、その中にある生命力を集めます。
蚕は黒い姿(新月)から白い姿(満月)へと、何度も脱皮しながら1ケ月かかって成長し、繭(満月)を作って変態します。
機織女は、月の生命力が凝縮した繭から絹を紡ぎ、光る衣(領巾・神衣・天の羽衣)を織り上げます。
規則正しく機を織る作業は、時と秩序と豊穣の月の特徴と重なります。
機織女は完成した領巾を振る呪術によって、月に生命力、光を返します。
また、馬を供犠として捧げます。
こうして、月は復活し、満ちゆき、馬の飛行力によって天高くで輝くことができるようになります。
<万葉集、出雲国風土記と月信仰>
「万葉集」に表現された世界観は、記紀神話に比較すると、政治的に改変された側面が少ないと思われます。
「万葉集」には月の歌は多く、太陽の歌は数少ないのです。
つまり、古代日本では、月信仰の方が強かったのです。
そして、「アマテル」という言葉は、月を形容する常套形容句(海を照らす月)でした。
つまり、「アマテル(アマラス)」は、本来は月の女神、あるいは、月の巫女神であり機織女を指す名前だったのでしょう。
実際、伊勢神宮の内宮の神楽歌にも、「アマテラス」を月とする歌が残っています。
また、内宮の秘伝書「倭姫命世紀」には、荒祭宮の多賀宮に祀られているアマテラスの和魂が「月天子」であると書かれています。
また、アマテラスの荒魂とされる「アマサカルムカツヒメ」の「天さかる向か」とは、月が西の天の極みに向かって昇ることを意味する常套句です。
さらには、本来の皇祖神であるタカミムスヒ(高木神)も槻に付く月神です。
「ムス」は再生を意味します。
そして、オオヒルメノムチ(=天照大神)はそれに仕える巫女です。
ちなみに、天皇を表す「スメラ」は月を表す「澄む」から来た言葉です。
また、天皇に名に現れる「タラシヒコ」の「足る」は月が満ちることを意味します。
*この項ここまで、三浦茂久「古代日本の月信仰と再生思想」を参照
三日月を表現する勾玉を神宝として重視する古代出雲には、月信仰が濃厚にあったはずです。
「出雲国風土記」に語られる加賀伝承は、月母神の創世神話だったはずですが、大和朝廷の意図によって改変されています。
本来の加賀伝承では、佐太大神の母、輝く支佐加比売(キサカヒヒメ)は月女神です。
洞窟の主であり、満月でもあったこの女神が、金の弓によって太陽を射落として新月の御子(=勾玉)である佐太大神(=オオナムチ)を生みました。
「加賀(カガ)」は、月光の輝きを意味します。
「佐太(サタ)」は、「更」+「足」、つまり、再生した満ちる月を意味します。
「猿田彦」も「佐太大神」と同じ神でしょう。
また、「出雲国風土記」に登場する神のアジスタカヒコは、大きな声で泣く児童神で、梯子を昇降します。
この神は、「変若水」垂らす新月、あるいは、「変若水」や稲妻として月から下り、また月に戻る神でしょう。
この神は、記紀神話のスサノオのモデルの一人だったのかもしれません。
*この項ここまで、ネリー・ナウマン「光の神話考古」掲載の坂田千鶴子「『出雲国風土記』砕かれた縄文槻神話の復元」を参照
<記紀神話と月信仰>
記紀神話は、縄文以来の月信仰を隠しました。
ですが、わずかに、その断片や改変された姿が残っています。
「日本書紀」では、月神のツクヨミがウケモチを殺すと、その死体の各所から穀物や蚕、牛馬が生まれます。 数少ない月に関する神話です。
この神話の背景には、月神が自然の死と再生を司る豊穣神と考えられていたことがあります。
「古事記」では、アマテラスが機屋で神に奉げる衣を織らせていた時、スサノオは機屋の屋根に穴を開けて、そこから皮を逆剥ぎにした天の斑馬を落とし入れます。
そのため、織織女が驚いて梭(ひ)で陰部を刺して死んでしまい、それに怒ったアマテラスは天岩屋に引き篭ります。
上に書いたように、馬は月の飛行力を象徴する動物であり、月神のツクヨミは馬に乗ります。
そのためか、馬は月神への犠牲獣でした。
スサノヲが馬を投げ入れたのは、馬を供犠にしたことが背景にあるのでしょう。
斑馬は月のような模様を持った馬であり、皮を剥がれているのは、光(=皮)を失った新月のことかもしれません。
であれば、岩戸に篭もったのは、アマテラス月女神です。
アマテラスは月の巫女であって、機屋に籠って、月を復活させる衣(=光)を織っていたのかもしれません。
また、アマテラスを岩屋から引き出す時に使った「鏡」は本来、満月の象徴でした。
「古事記」の出雲神話である「因幡の白兎」にも、その古層に月の神話があったと思われます。
因幡の白兎は海峡を渡るため、ワニを騙して一列に並ばせたワニの上を数えながら渡っていきますが、最後に嘘がばれて皮を剥がれます。
白兎が泣いていると、オオナムチが来て、治療法を教えてくれて治ります。
兎は月の明部の象徴ですから、ワニは暗部の象徴でしょう。
ワニを数えて海を渡るのは、月を読むこと(ツクヨミ)、つまり日を数えることです。
白兎が皮を剥がれるのは、満月が徐々に欠けて新月になるからです。
白兎が泣くのは、月が「変若水」を自然に降らすためです。
オオナムチには、復活した新月の神という性質が隠れています。
<月神話の心理学的意味>
太陽が意識的自我の象徴なら、月は無意識的な自己の象徴です。
古代の世界観においては、後者を重視し、後者が前者の創造力の基盤でした。
特に、狩猟文化では、女性原理の生む力を信仰し、人工的に田畑を管理する農耕文化とは違って、自然の森の中へ動物を迎えに行くので、後者を重視します。
太陽の死と再生を考えることは、意識の創造力を考えることです。
ですが、月の死と再生を考えることは、無意識の創造力を考えることです。
後者は、前者の基盤です。
月の死と再生を心に刻むことは、より深い創造力と、人格の成熟を導くことができます。
狩猟文化と原地母神信仰 [伝統文化のコスモロジー]
農業や牧畜が発明される以前の後期旧石器時代の現生人類の文化は、狩猟・採集・漁撈文化(以下、狩猟文化)でした。
この文化は、現在まで、一部の地域で生き残っていますし、その宗教的影響は各所に大きく残っています。
このページでは、典型的・原型的な「狩猟文化」のコスモロジーを、「農耕文化」(別ページで扱います)と対比してモデル化します。
狩猟文化は、「遊動」から「定住」へと以降して大きく変化しましたが、両方を含めて「狩猟文化」として扱い、最後に「遊動文化」と「定住文化」の違いを簡単にまとめます。
また、シャーマニズム的には「狩猟文化」と類似する「牧畜(遊牧)文化」についても、簡単に触れます。
多くの狩猟・採集文化は、食料の大部分を採集に頼っていますが、狩猟には部族の世界観の核となるような宗教的な意味がありました。
男性が狩猟、女性が採集を担当し、脱魂・飛翔型の男性のシャーマンが、霊的世界とのコミュニケーションを担いました。 そして、豊猟を保証する宗教的儀式、呪術などの役割は、シャーマンが「動物の女主」を相手として行いました。
狩猟や脱魂は、「死」に関わるものであり、また、女性を対象とするものであるため男性の担当なのです。
一方、農耕文化では、伐採、耕作は男性が行いましたが、これは、植物や大地を殺すものだからでしょう。
農耕文化では、憑霊型の女性シャーマンが霊的存在を招きますが、これは男性神をこの世へ誕生させるものであるため、女性の担当なのです。
<原地母神(太母)>
どんな原始的な文化でも、ほとんどの場合は天上に至高の神がいると考えています。
ですが、この神は、ほとんど人間に関係せず、人間も関心を寄せないことが多いようです。
狩猟文化においては、天上世界はあまり大きな意味を持たず、地下世界との関係が重要でした。
狩猟文化では、「原地母神(太母)」と呼べるような女神が最も重要な存在でした。
この言葉は、農耕文化で信仰される「地母神」と対比して使っています。
原地母神は地下や海底の冥界にいて、生命を生む根源的な力を持つ存在です。
すべてを生み育て、魂の循環を司る「母」です。
「原地母神」には、人間を生む「人間の母」という側面と、動・植物を生む「動・植物の母(主、山ノ神)」、天体や自然を生む創造母神、火を生む「竈神」、あるいは大地そのものである「地母神」、あの世を主宰する「冥界母神」といった様々な側面があります。
後世には、それぞれの側面がそれぞれの神格として分かれていきました。
「原地母神」はお尻やお乳の大きい姿、あるいは子供を生んでいる姿で表されることが多くあります。
また、2匹の豹や獅子に守護された姿などで表されます。
「動物の女主」である「原地母神」は、半人半獣の姿で表されることもあります。
狩る動物の代表は「豹」、「獅子」など、狩られる動物の代表は「牛」、「鹿」などです。
また、大地の豊饒の象徴である「ヒキガエル」、あるいは「石(隕石、隕鉄)」、「渦巻き」や「迷宮」などの図形も「原地母神」の象徴でした。
天・地・地下を貫いて世界の中心に生えていると考えられた「世界樹」や「生命の樹」に代表される「樹」も「原地母神」の象徴、あるいは、依代でした。
「原地母神(動物の女主)」は、食物や動物の魂を無限に生む「袋(釜、鍋)」を持っていると考えられました。
これは地母神の「子宮」だとも言えます。
この袋は骨から動物を再生することもできます。
「洞窟」は最も身近な他界であり、冥界への入口でした。
大地が「原地母神」の体なら、洞窟はその「子宮(女陰)」でした。
人間が一生を終えて入る「墓」や、毎夜に戻る「家」も、地下冥界のあの世に戻るための原地母神の「子宮」と考えられました。
また、原地母神の子供である「火」が生まれる「竈」や、様々な食事を育む「土器」もそうです。
「原地母神」は「父性原理」を必要とせずに一人で様々な存在を生み出す「両性具有」的存在です。
ですが、「原地母神」の創造を助ける産婆役として、「原地母神」の一部である「男性原理」が「息子(恋人)」として分離して考えられることもありました。
この「原地母神」の「男性原理」は「男根」で象徴されます。
「父性原理」でないので全身を持つ神像ではないのです。
つまり、「原地母神」は、本来、自分の一部である「息子」によって自己受精するのです。
ですから、「原地母神」(その象徴の樹)には動物や人間の男根や睾丸が捧げられることもありました。
これに対して、農耕文化の「地母神」は、太陽神、嵐神などの天の「父神」と対になる存在です。
地上の存在は、人間も動物も、植物も、鉱物も、太陽などの天体も、すべて「原地母神」の子供です。
そのため、それらはすべて人間の親戚であり、その魂にも本質的な違いはありません。
地上で仮に違う姿をしているだけです。
地上の存在の代表は、「原地母神」の男性原理である「息子」の役割を演じることもあります。
人間の代表は、狩人でもある「シャーマン」です。
天体の代表は「太陽」です。
狩人のヤリは男根、太陽の光は精子の象徴になりました。
太陽は「原地母神」の息子なので、「原地母神」の子宮である洞窟から生まれたり、あるいは、「原地母神」の目、あるいは、「原地母神」と一体である世界樹に咲く花だと考えられたりしました。
また、太陽は「原地母神」の恋人なので、洞窟に光を指すことで自分の復活も含めた自然の豊饒をもたらすと考えられました。
<狩り、動物の女主、再生儀礼>
人間や動物の魂は、現世と冥界を循環します。
この世で死ぬことは、あの世の「原地母神(冥界母神、動物の女主)」の元へ戻ることであり、そこからこの世に誕生します。
ですから、魂を「原地母神」の元に送り、「原地母神」の力によって再生させる「再生儀礼」が、狩猟文化の宗教の核心です。
狩り、食事、葬式は、魂を送り返す一連の行為であり、「再生儀礼」と一体のものです。
狩りには、人間が主体的に狩るのではなく、肉体という贈り物を持ってくる動物を迎えに行くといった感覚があります。
ですから、狩りは礼儀正しく正々堂々と行わなければいけません。
非人道的な作戦や強力過ぎる武器は使えません。
狩りの後には、動物の魂をなだめ、死体を丁寧に扱い、礼儀に従って食し、お返しの贈り物を持たせて「動物の女主」の元に送る儀式が必要でした。
でないと、動物は2度と人間の前に姿を現さなくなります。
動物の供犠も、魂を「原地母神」のところに送り返すことの象徴的な儀式でした。
動物や人間の「骨」、特に「頭蓋骨」は不滅の魂の象徴として、「動物の女主」を象徴する樹に架けるなどして祀りました。
そして、「血」が再生の力の象徴として振りかけられました。
色で言えば、基本的に、赤は再生力の象徴であり、緑(青)は成長力の象徴です。
シャーマンは不猟の時には、別ページで紹介したように、脱魂して「動物の女主」から必要な魂をもらいます。
また、別ページで紹介したように、洞窟で儀礼を行いました。
シャーマンは「原地母神」に自らを捧げるために、傷をつけたり、神話的には「樹」に吊り下げられたりすることもあります。
タロットカードの「吊るされた男」や十字架のキリストの源流もここにあります。
狩猟文化のシャーマン的な神秘思想を考えると、その核心は、日常的な自我を殺すことによって、「原地母神」として表される創造力に合一し、再生することです。
また、類似した意味を持つ儀礼として、部族文化の成人のイニシエーション儀礼があります。
これは、怪物のような存在、あるいは、熊や虎、クジラなどに飲み込まれて、吐き出されるという擬死再生の体験を基本としています。
この怪物のような存在は、「原地母神」の化身的な存在であって、この擬死再生儀礼は、狩猟文化の魂の循環の秘密を体現して知ることなのです。
また、この怪物に食べられて再生することは、人間が動物を食べて冥界に送り返すことと、ちょうど対称的です。
<男性神の巡回>
「原地母神」の子供である地上の生物、その代表である男性神は、季節によって、地上と冥界(原地母神の元)を循環すると考えられました。
神話にもそれは反映されましたが、地域によって、その神話は異なります。
例えば、ケルト人などの地域では、獣王(ケルヌンノスなど)が、冬に冥界に降りて地母神とカップルになり、春に地上に上がると、冥界王が地母神とカップルになると考えたようです。
また、漁撈が重要な地域(おそらく縄文人やその後継の海の民、アイヌも)では、「海の神(ワニ=サメ、シャチ=エビス)」が、冥界である山の女神の元へ、川を遡る、あるいは、洞窟の中を登る、特別な神の道を通るなどして、通うと考えたようです。
ちなみに、死者の魂も、海岸の洞窟から山中地下の他界を経て、山頂から天の世界へ行くと考えました。
<冬至祭>
狩猟文化では、太陽を初めとして、すべての生命が衰退から復活へと転じる象徴的な日である「冬至」が、最も重要な祭儀の日でした。
「立石」や「立柱」は、「環状列石」や近方の山などと太陽を基準にして、季節を知るカレンダーでもありましたが、太陽の光を受けてその魂や精子を宿す依代でもありました。
そのため、「立石」は冥界への入り口でもありました。
そのため、冬至に昇る太陽の光や「立石」の影が、家の中の竈に差すように配置されました。
これは「原地母神」を自己受精させて、自然の豊饒を祈る再生儀礼です。
「冬至祭」では、新しい「火」が鑽り出されました。
「火」は「原地母神」の子であり、生命力です。
新しい「火」は、各家庭の竈にもたらされ、家の守り神として1年間保持されました。
また、村の境界にも、魔除けと豊饒のために、男根としての「立石」が立てられたり、子宮としての「壷」が埋められたりしました。
境界神や道祖神の源流です。
<月信仰>
狩猟文化には、月信仰が強くありました。
満ち欠けを繰り返す月信仰には、太陽信仰よりも復活の観念が強くあります。
また、女性や水とのつながりが大きいものです。
そのため、月信仰は、「原地母神」の女性原理と再生力を中心とする狩猟文化とつながりが強いのです。
ですが、月信仰に関しては、別ページの「縄文文化と月信仰」で扱います。
<遊動文化と定住文化>
初期の狩猟文化は、数家族からなる流動的なバンド単位で、定住せずに移動生活を行っていました。
ですが、徐々に、主に漁撈の生産量が多い場所から定住生活が生まれました。
日本では縄文時代の早期に定住化が行われました。
遊動文化では、家族制度は、双系で、出自が組織化されておらず、従って、「家系」という観念を伴いませんでした。
ですが、定住にともなって、氏族社会が成立し、出自が女系、もしくは男系に組織化されます。
これに伴って「先祖」は、一つの「家系(氏)」の先祖となります。
そのため、「先祖」は純粋に普遍的な霊魂ではなく、氏族としての個性を持つ存在になります。
遊動文化では、食料は平等に分配し、蓄積がなく、「純粋贈与」(得たものをただ与える)という交換様式のみを行っていました。
ですが、定住生活によって、初期の蓄積、格差が発生し、共同体の中での「互酬」(何かを与えられると、何かを返す)という交換様式が始まります。
また、定住によって、空間の宗教的意味の分節化が進んだでしょう。
村の中と外、中心と周縁、四方の観念などが強化されました。
<牧畜(遊牧)文化>
牧畜・遊牧文化は、動物性の生産を中心にしている点では、狩猟文化と共通します。
ですが、その動物は、神(動物の女主)が管理する野生の動物ではなく、人間が管理する家畜です。
その点では、農耕文化と同じです。
遊牧は、移動生活を営みますが、年周期での移住場所がほぼ決まっている点で、定住でも遊動でもなく、その中間的性質を持っています。
遊牧文化は、狩猟文化と同様に脱魂型の男性シャーマンが多いのですが、動物の管理は、星座などの天の情報によるからか、地下世界の精霊よりも、天上の神(テングリ信仰)に対する信仰が強いのが特徴です。
この文化は、現在まで、一部の地域で生き残っていますし、その宗教的影響は各所に大きく残っています。
このページでは、典型的・原型的な「狩猟文化」のコスモロジーを、「農耕文化」(別ページで扱います)と対比してモデル化します。
狩猟文化は、「遊動」から「定住」へと以降して大きく変化しましたが、両方を含めて「狩猟文化」として扱い、最後に「遊動文化」と「定住文化」の違いを簡単にまとめます。
また、シャーマニズム的には「狩猟文化」と類似する「牧畜(遊牧)文化」についても、簡単に触れます。
多くの狩猟・採集文化は、食料の大部分を採集に頼っていますが、狩猟には部族の世界観の核となるような宗教的な意味がありました。
男性が狩猟、女性が採集を担当し、脱魂・飛翔型の男性のシャーマンが、霊的世界とのコミュニケーションを担いました。 そして、豊猟を保証する宗教的儀式、呪術などの役割は、シャーマンが「動物の女主」を相手として行いました。
狩猟や脱魂は、「死」に関わるものであり、また、女性を対象とするものであるため男性の担当なのです。
一方、農耕文化では、伐採、耕作は男性が行いましたが、これは、植物や大地を殺すものだからでしょう。
農耕文化では、憑霊型の女性シャーマンが霊的存在を招きますが、これは男性神をこの世へ誕生させるものであるため、女性の担当なのです。
<原地母神(太母)>
どんな原始的な文化でも、ほとんどの場合は天上に至高の神がいると考えています。
ですが、この神は、ほとんど人間に関係せず、人間も関心を寄せないことが多いようです。
狩猟文化においては、天上世界はあまり大きな意味を持たず、地下世界との関係が重要でした。
狩猟文化では、「原地母神(太母)」と呼べるような女神が最も重要な存在でした。
この言葉は、農耕文化で信仰される「地母神」と対比して使っています。
原地母神は地下や海底の冥界にいて、生命を生む根源的な力を持つ存在です。
すべてを生み育て、魂の循環を司る「母」です。
「原地母神」には、人間を生む「人間の母」という側面と、動・植物を生む「動・植物の母(主、山ノ神)」、天体や自然を生む創造母神、火を生む「竈神」、あるいは大地そのものである「地母神」、あの世を主宰する「冥界母神」といった様々な側面があります。
後世には、それぞれの側面がそれぞれの神格として分かれていきました。
「原地母神」はお尻やお乳の大きい姿、あるいは子供を生んでいる姿で表されることが多くあります。
また、2匹の豹や獅子に守護された姿などで表されます。
「動物の女主」である「原地母神」は、半人半獣の姿で表されることもあります。
狩る動物の代表は「豹」、「獅子」など、狩られる動物の代表は「牛」、「鹿」などです。
また、大地の豊饒の象徴である「ヒキガエル」、あるいは「石(隕石、隕鉄)」、「渦巻き」や「迷宮」などの図形も「原地母神」の象徴でした。
天・地・地下を貫いて世界の中心に生えていると考えられた「世界樹」や「生命の樹」に代表される「樹」も「原地母神」の象徴、あるいは、依代でした。
「原地母神(動物の女主)」は、食物や動物の魂を無限に生む「袋(釜、鍋)」を持っていると考えられました。
これは地母神の「子宮」だとも言えます。
この袋は骨から動物を再生することもできます。
「洞窟」は最も身近な他界であり、冥界への入口でした。
大地が「原地母神」の体なら、洞窟はその「子宮(女陰)」でした。
人間が一生を終えて入る「墓」や、毎夜に戻る「家」も、地下冥界のあの世に戻るための原地母神の「子宮」と考えられました。
また、原地母神の子供である「火」が生まれる「竈」や、様々な食事を育む「土器」もそうです。
「原地母神」は「父性原理」を必要とせずに一人で様々な存在を生み出す「両性具有」的存在です。
ですが、「原地母神」の創造を助ける産婆役として、「原地母神」の一部である「男性原理」が「息子(恋人)」として分離して考えられることもありました。
この「原地母神」の「男性原理」は「男根」で象徴されます。
「父性原理」でないので全身を持つ神像ではないのです。
つまり、「原地母神」は、本来、自分の一部である「息子」によって自己受精するのです。
ですから、「原地母神」(その象徴の樹)には動物や人間の男根や睾丸が捧げられることもありました。
これに対して、農耕文化の「地母神」は、太陽神、嵐神などの天の「父神」と対になる存在です。
地上の存在は、人間も動物も、植物も、鉱物も、太陽などの天体も、すべて「原地母神」の子供です。
そのため、それらはすべて人間の親戚であり、その魂にも本質的な違いはありません。
地上で仮に違う姿をしているだけです。
地上の存在の代表は、「原地母神」の男性原理である「息子」の役割を演じることもあります。
人間の代表は、狩人でもある「シャーマン」です。
天体の代表は「太陽」です。
狩人のヤリは男根、太陽の光は精子の象徴になりました。
太陽は「原地母神」の息子なので、「原地母神」の子宮である洞窟から生まれたり、あるいは、「原地母神」の目、あるいは、「原地母神」と一体である世界樹に咲く花だと考えられたりしました。
また、太陽は「原地母神」の恋人なので、洞窟に光を指すことで自分の復活も含めた自然の豊饒をもたらすと考えられました。
<狩り、動物の女主、再生儀礼>
人間や動物の魂は、現世と冥界を循環します。
この世で死ぬことは、あの世の「原地母神(冥界母神、動物の女主)」の元へ戻ることであり、そこからこの世に誕生します。
ですから、魂を「原地母神」の元に送り、「原地母神」の力によって再生させる「再生儀礼」が、狩猟文化の宗教の核心です。
狩り、食事、葬式は、魂を送り返す一連の行為であり、「再生儀礼」と一体のものです。
狩りには、人間が主体的に狩るのではなく、肉体という贈り物を持ってくる動物を迎えに行くといった感覚があります。
ですから、狩りは礼儀正しく正々堂々と行わなければいけません。
非人道的な作戦や強力過ぎる武器は使えません。
狩りの後には、動物の魂をなだめ、死体を丁寧に扱い、礼儀に従って食し、お返しの贈り物を持たせて「動物の女主」の元に送る儀式が必要でした。
でないと、動物は2度と人間の前に姿を現さなくなります。
動物の供犠も、魂を「原地母神」のところに送り返すことの象徴的な儀式でした。
動物や人間の「骨」、特に「頭蓋骨」は不滅の魂の象徴として、「動物の女主」を象徴する樹に架けるなどして祀りました。
そして、「血」が再生の力の象徴として振りかけられました。
色で言えば、基本的に、赤は再生力の象徴であり、緑(青)は成長力の象徴です。
シャーマンは不猟の時には、別ページで紹介したように、脱魂して「動物の女主」から必要な魂をもらいます。
また、別ページで紹介したように、洞窟で儀礼を行いました。
シャーマンは「原地母神」に自らを捧げるために、傷をつけたり、神話的には「樹」に吊り下げられたりすることもあります。
タロットカードの「吊るされた男」や十字架のキリストの源流もここにあります。
狩猟文化のシャーマン的な神秘思想を考えると、その核心は、日常的な自我を殺すことによって、「原地母神」として表される創造力に合一し、再生することです。
また、類似した意味を持つ儀礼として、部族文化の成人のイニシエーション儀礼があります。
これは、怪物のような存在、あるいは、熊や虎、クジラなどに飲み込まれて、吐き出されるという擬死再生の体験を基本としています。
この怪物のような存在は、「原地母神」の化身的な存在であって、この擬死再生儀礼は、狩猟文化の魂の循環の秘密を体現して知ることなのです。
また、この怪物に食べられて再生することは、人間が動物を食べて冥界に送り返すことと、ちょうど対称的です。
<男性神の巡回>
「原地母神」の子供である地上の生物、その代表である男性神は、季節によって、地上と冥界(原地母神の元)を循環すると考えられました。
神話にもそれは反映されましたが、地域によって、その神話は異なります。
例えば、ケルト人などの地域では、獣王(ケルヌンノスなど)が、冬に冥界に降りて地母神とカップルになり、春に地上に上がると、冥界王が地母神とカップルになると考えたようです。
また、漁撈が重要な地域(おそらく縄文人やその後継の海の民、アイヌも)では、「海の神(ワニ=サメ、シャチ=エビス)」が、冥界である山の女神の元へ、川を遡る、あるいは、洞窟の中を登る、特別な神の道を通るなどして、通うと考えたようです。
ちなみに、死者の魂も、海岸の洞窟から山中地下の他界を経て、山頂から天の世界へ行くと考えました。
<冬至祭>
狩猟文化では、太陽を初めとして、すべての生命が衰退から復活へと転じる象徴的な日である「冬至」が、最も重要な祭儀の日でした。
「立石」や「立柱」は、「環状列石」や近方の山などと太陽を基準にして、季節を知るカレンダーでもありましたが、太陽の光を受けてその魂や精子を宿す依代でもありました。
そのため、「立石」は冥界への入り口でもありました。
そのため、冬至に昇る太陽の光や「立石」の影が、家の中の竈に差すように配置されました。
これは「原地母神」を自己受精させて、自然の豊饒を祈る再生儀礼です。
「冬至祭」では、新しい「火」が鑽り出されました。
「火」は「原地母神」の子であり、生命力です。
新しい「火」は、各家庭の竈にもたらされ、家の守り神として1年間保持されました。
また、村の境界にも、魔除けと豊饒のために、男根としての「立石」が立てられたり、子宮としての「壷」が埋められたりしました。
境界神や道祖神の源流です。
<月信仰>
狩猟文化には、月信仰が強くありました。
満ち欠けを繰り返す月信仰には、太陽信仰よりも復活の観念が強くあります。
また、女性や水とのつながりが大きいものです。
そのため、月信仰は、「原地母神」の女性原理と再生力を中心とする狩猟文化とつながりが強いのです。
ですが、月信仰に関しては、別ページの「縄文文化と月信仰」で扱います。
<遊動文化と定住文化>
初期の狩猟文化は、数家族からなる流動的なバンド単位で、定住せずに移動生活を行っていました。
ですが、徐々に、主に漁撈の生産量が多い場所から定住生活が生まれました。
日本では縄文時代の早期に定住化が行われました。
遊動文化では、家族制度は、双系で、出自が組織化されておらず、従って、「家系」という観念を伴いませんでした。
ですが、定住にともなって、氏族社会が成立し、出自が女系、もしくは男系に組織化されます。
これに伴って「先祖」は、一つの「家系(氏)」の先祖となります。
そのため、「先祖」は純粋に普遍的な霊魂ではなく、氏族としての個性を持つ存在になります。
遊動文化では、食料は平等に分配し、蓄積がなく、「純粋贈与」(得たものをただ与える)という交換様式のみを行っていました。
ですが、定住生活によって、初期の蓄積、格差が発生し、共同体の中での「互酬」(何かを与えられると、何かを返す)という交換様式が始まります。
また、定住によって、空間の宗教的意味の分節化が進んだでしょう。
村の中と外、中心と周縁、四方の観念などが強化されました。
<牧畜(遊牧)文化>
牧畜・遊牧文化は、動物性の生産を中心にしている点では、狩猟文化と共通します。
ですが、その動物は、神(動物の女主)が管理する野生の動物ではなく、人間が管理する家畜です。
その点では、農耕文化と同じです。
遊牧は、移動生活を営みますが、年周期での移住場所がほぼ決まっている点で、定住でも遊動でもなく、その中間的性質を持っています。
遊牧文化は、狩猟文化と同様に脱魂型の男性シャーマンが多いのですが、動物の管理は、星座などの天の情報によるからか、地下世界の精霊よりも、天上の神(テングリ信仰)に対する信仰が強いのが特徴です。



